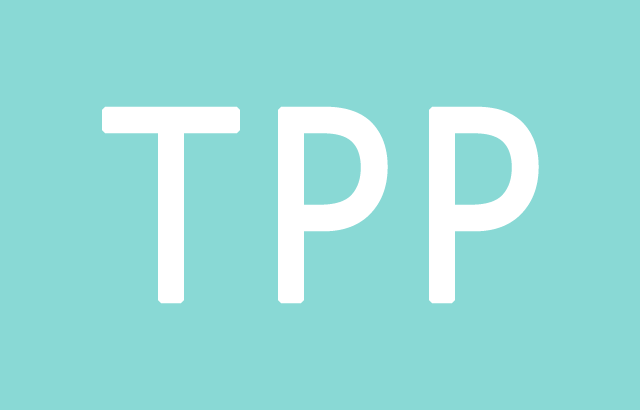ジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)は、特に若い稲に対する食害を引き起こす害虫として知られています。南米原産の大型の巻貝であるジャンボタニシは、かつて食用として日本に輸入され、全国各地で養殖されていました。その後、野生化したものが主に水田や農業用水路に生息するようになり、現在では害虫として知られています。
本記事ではそんな水稲栽培の厄介者であるジャンボタニシの生態と対策、そして注目を集める肥料としての利用可能性について紹介していきます。
ジャンボタニシの生態


ジャンボタニシは繁殖力が非常に高く、年間で3,000個以上の卵を産みます。卵は特徴的な濃いピンク色をしています。ひと塊200〜300個の卵は、水上の植物体や水路の外壁に産み付けられます。孵化までの期間は温度25℃で約2週間で、生まれた貝は秋までに成長し、殻の大きさは1〜3cm程度に達します。冬季は土の中に潜って越冬し、春になると再び水田に現れます。
ジャンボタニシは乾燥に強く、水がなくても半年以上生存する一方で、寒さには弱く、気温がマイナス3℃を下回ると多くの個体が死に至ります。しかし近年は暖冬の影響で、ジャンボタニシが越冬できる場所が増え、その生存率が高まっています。その結果、発生地域が広がっています。暖冬のほか、温暖な地域では越冬が容易になることから、前述したように、越冬した個体は春には水田に戻って活動を始めます。
ジャンボタニシによる食害は、特に稲の苗が小さい3〜4葉期によく見られます。田植え後、約3週間以内の柔らかい苗を好むため、5葉期になるとほとんど食害はありません。
なお、水田内では、畦際や取水口・排水口付近など、水深が深くなりやすい場所はジャンボタニシが集まりやすい場所であり、被害を受けやすい場所とされています。
ジャンボタニシ対策


ジャンボタニシは若い稲を好み、田植え後3週間程度の間に食害を受けやすいため、早期の対策が必要です。ジャンボタニシ対策には以下のものがあげられます。
取水口網の設置
取水口や排水口にネットや金網を設置することで、水田へのジャンボタニシの侵入を防ぎます。大型の貝が水田に入るのを防ぐのに最適なネットの目合いは約9mmです。田植え前から移植後3週間まで設置し、水田内の個体密度の低減に努めます。
田植え後の浅水管理
水深を4cm(理想は1cm)以下に維持することで、貝の摂食活動を抑制することができます。特に田植え後の若苗期に浅水管理を行ったり、水田の均平化を保ち、水深が深くなる場所を減らしたりすることが重要です。
冬期の耕うん
ジャンボタニシの生態で記述したように、ジャンボタニシは寒さに弱いため、寒さをしのぐために土の中に潜って越冬します。落ち葉や泥が溜まった水路や稲を刈った後、翌春まで耕うんしない水田は、ジャンボタニシが土に潜って寒さをしのぐのに適した場所となります。
そこで、厳寒期にトラクターで土壌を細かく砕き、ジャンボタニシの越冬個体を物理的に破砕する方法が効果的です。貝の生存率を減少させるため、耕うんは貝が越冬する深さ6cm以内をターゲットに行います。
石灰窒素の散布
秋期や春季に石灰窒素を散布することも効果的です。秋期の散布は、収穫後、水温が17℃以上の時期に湛水してから行います。春期は田植え前に散布し、2〜3日間湛水を保った後に代かきを行ってください。ただし、石灰窒素は魚毒性が高いため、水路への流出を防ぐ必要がある点に注意してください。
貝と卵塊の捕殺
ジャンボタニシの卵塊を見つけた場合には、潰すなどの方法で孵化を防ぎます。また、成貝を定期的に捕殺することも効果的です。ただし、卵や貝には寄生虫が含まれていることがあります。素手では触れず、捕殺後は手洗いを徹底してください。
ジャンボタニシの活用術


水稲栽培において害虫とされるジャンボタニシですが、肥料としての利用法が注目されています。というのも、貝の殻に多く含まれるカルシウムやマグネシウムが農業用の有機肥料として利用できる可能性があるからです。
たとえば、2022年5月18日、日本農業新聞のウェブサイトで公開された記事によると、京都府立洛西高校の生徒たちは、地元の住民団体と連携し、大原野地域で捕獲したジャンボタニシを肥料として活用する試みを行いました。彼らが開発したのは、ジャンボタニシを間伐した竹とともに焼却し、その炭化物を肥料として利用する方法です。この方法により、竹林整備とジャンボタニシ被害の軽減を同時に行うことができます。さらに、この活動を支援する京都市南部農業振興センターによると、この肥料は小松菜やハツカダイコンの栽培において、対照区よりも良好な成長を促進したことが確認されています。
同じく日本農業新聞で2024年3月6日に公開された記事では、愛媛県によるジャンボタニシの「飼料」化の研究が取り上げられています。愛媛県養鶏研究所は、ジャンボタニシを採卵鶏の飼料に転用する実証試験を行い、その成果として、ジャンボタニシを加熱・乾燥処理し粉砕した飼料が、たんぱく質やカルシウムの代替として有望であることが示され、さらにひな鶏の成長や採卵鶏の嗜好性に問題なく使用できることを確認しました。
これらの事例は、ジャンボタニシが資源として再利用できる可能性を示しています。もちろん、コスト面など調査すべき点はまだ多いのが現状ですが、水田に被害を及ぼすジャンボタニシを取り除きつつ、無駄なく活用すること、特に、肥料や飼料としての活用は、環境負荷を減らし、農業における資源循環の促進につながることが期待されます。
参照サイト