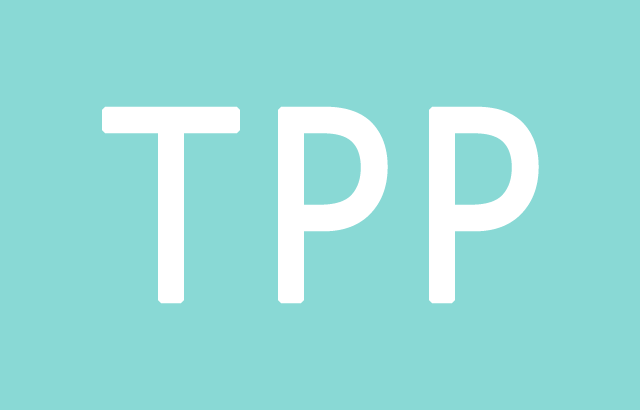イネカメムシとは、水稲栽培における害虫で、近年全国的に発生が増加している斑点米カメムシ類の一種です。1960年代以降に国内での発生量が減少していましたが、近年では温暖化の影響や、経営規模の大規模化、新規需要米の増加により作期が異なる品種が栽培されるようになったことで、発生量が増加しています。
イネカメムシによる被害


※画像は斑点米カメムシ。イネカメムシの詳細(成虫や幼虫の姿など)については「イネカメムシの生態、被害、 および防除法について|農林水産省」をご参照ください。
イネカメムシは水稲の穂を吸汁し、不稔や斑点米を生じさせ、減収の原因となります。特に出穂期から登熟初期に加害が始まります。このため、出穂が早い圃場では集中して発生する可能性が高く、注意が必要です。
イネカメムシの生態


イネカメムシの体長は12〜13mm、色は茶褐色です。カメムシはその種類によって頭部の側葉(側方から見て複眼の中央と頭頂を結ぶ縁より上)の形が異なるのですが、イネカメムシの場合、頭部の側葉が左右で接しておらず、角ばって見えるのが特徴です。
イネカメムシは、成虫が越冬し、春先から雑草地に移動して繁殖します。7月中旬から下旬にかけて、成虫は水田へと侵入し、出穂した稲を加害します。昼間は株元に隠れていることが多く、夜間に加害活動を行います。
他の斑点米カメムシ類と異なり、イネに対する嗜好性が非常に高く、畦畔や水田周辺のイネ科雑草で確認されることが少ないといった特徴もあります。
他の斑点米カメムシ類は基本的に水田内では増殖せず、イネ科雑草上で越冬した成虫が水田周辺の雑草地で増殖しますが、越冬場所から出てきたイネカメムシの成虫は出穂直後の水田に直接飛来して産卵します。そのため、他のカメムシ類の防除対策として有効な「雑草の除去」が効果的ではない点に注意が必要です。
防除策


前述した通り、他の斑点米カメムシ類とは異なる点があり、たとえば雑草の除去は防除策として有効ではありません。
防除対策として最も重要なのは、出穂期前の早期防除です。不稔籾の発生を防止するためには、出穂直後の吸汁を押さえることが特に重要です。出穂直後に加害を受けることが多いため、ジノテフラン剤やエチプロール剤などの殺虫剤を使用して、出穂前にしっかりと防除を行うことが推奨されています。特に、イネカメムシの発生が多い地域では、指導機関に相談して防除計画を立てることが有効です。
出穂期もイネカメムシの発生状況を確認し、発生が認められる場合は追加防除を実施してください。特に、周囲よりも出穂が早いまたは遅い圃場では、イネカメムシによる被害が多くなる可能性があるため注意が必要です。
加えて重要なのが、収穫後の速やかな耕うんです。収穫時期の水田から移動したとみられる成虫が、ヒコバエの穂に多数寄生している様子が見つかっているため、刈株を埋没・枯死させて、イネカメムシが越冬する場所を減らすことが防除対策となります。
なお、稲株の早期すき込みは、イネカメムシ以外の害虫にも効果があり、雑草の管理にも役立ちます。これにより、翌年の田植え後の活着がスムーズになり、大雨による稲わらの流出や散乱も抑制できます。
参照サイト