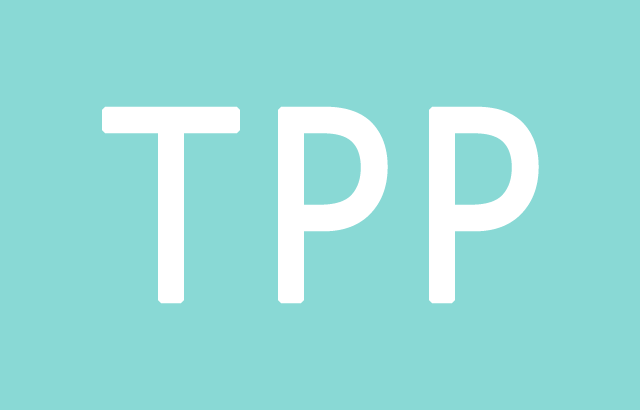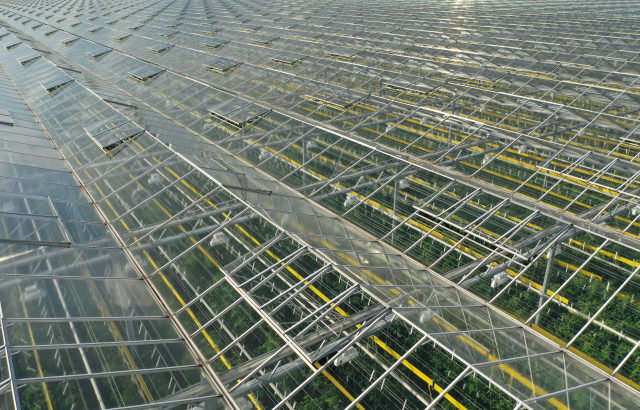日本の農林水産物の輸出金額は2023年で1兆4,547億円(少額貨物輸出額を含む)で、主な輸出先は中国、香港、アメリカ、台湾、韓国などです。
かねてより、日本政府は「日本食に使われる食材を輸出することで農業の競争力を高める」との期待を込めて、2020年までに輸出金額を1兆円に増やす目標を掲げていました。輸出農産物は食料自給率にも影響を与えることから、輸出金額の増加は自給率向上にも貢献すると期待が寄せられています。
日本の農業界では、国内市場の縮小に伴い、海外市場への進出が重要な成長戦略として注目されています。そのため、各国のニーズに合わせた対応や日本産農産物のブランディング強化が急務となっています。
サイズ分けに役立つデジタル技術


農産物の輸出において、特に金額が多い品目は牛肉、リンゴ、ナガイモなどです。
なお、国によって農産物の評価基準はまったく異なります。リンゴの場合、国内では大玉のリンゴが好まれますが、たとえばイギリスでは大きなリンゴは加工用としてしか使われず、小玉のリンゴが好まれます。そのため、各国のニーズに合わせた対応が求められます。
そこで注目を集めているデジタル技術が、選果自動化技術です。果物の選果工程の自動化は、品質の管理や作業効率を高め、輸出拡大に向けて大きな役割を果たします。
最新の選果自動化技術には、光学選別機、AI搭載選果システム、非破壊内部品質検査などがあります。これらの技術は、従来の外観や重量だけでなく、果実内部の品質も評価できる高度なシステムです。
日本産リンゴの輸出を手がける株式会社日本農業は、青森県産のリンゴ選果において、オランダ・GREEFA社製の大型選果機を導入しました。この新しい選果機は、従来の3倍の処理能力を持ち、1秒で8個のリンゴを選別可能です。これまでは熟練の作業員が目視で判別作業を行っていましたが、機械化により「見落とし」を減らせるだけでなく、選果量の増加が可能になることで、国内外の需要に迅速に対応できる体制が整います。また、経験が少ない作業員でも選果・梱包作業が可能になったり、生産者の作業負担を軽減したり、あらゆる面に貢献しています。
選果自動化技術は、日本産農産物の輸出拡大と品質維持において重要な役割を果たし、国内外での競争力を高めるための鍵といえます。
国際認証の取得に役立つデジタル技術


海外市場での競争力を高めるために
近年、日本の農産物輸出が急増している背景には、世界的な日本食ブームや旅行先としての日本人気の高まりがあります。特に、香港や中国などのアジア諸国・地域で所得の増加に伴い、購買力が旺盛で、日本産農産物の需要が拡大しています。
しかし日本産の農産物にはいくつかの課題があります。たとえば、価格が高めであることは消費者にとって一つの障壁となっています。日本産は品質が高く、安全であるというイメージがありますが、それが今後簡単に通用するとは限りません。
また、アメリカの流通大手のように、取引条件にグローバルGAP取得を加える企業も増えており、それらへの対応も課題といえます。
グローバルGAPとは簡潔にいうと、適正な農業の取り組みを証明する国際基準です。GAPは「Good Agricultural Practices(グッド・アグリカルチュラル・プラクティス)」の略称で、一般的には「農業生産工程管理」と呼ばれます。農業において、食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための取組です。第三者機関が農場の取り組みをチェックすることで、消費者に対して品質と安全性を証明することができます。
日本の農業が海外市場で競争力を保ち、さらに拡大するためには、これらの国際認証を積極的に取得し、品質保証を強化することが求められます。農家や事業者がグローバルGAPの取得に対応することは、海外市場での信頼性を高めることにつながります。
国際認証に役立つデジタル技術
農業の品質管理に欠かせないグローバルGAP(Good Agricultural Practices)認証の取得には、デジタル技術が大いに役立ちます。
たとえば、「アグリノート」という農業ICTツールは、農場の航空写真を用いて圃場の管理や作業記録を可視化し、情報の共有をサポートします。このツールは、農作業の記録をスマートフォンやタブレットからも入力・閲覧できる機能を備えており、農業生産活動の効率化に貢献します。
また、前述の「アグリノート」と連携するNECの「GAP認証支援サービス」は、農業生産に関わるさまざまな情報をGAPの「点検項目」に基づいて整理し、実施状況を可視化することで、認証取得を支援します。これにより、生産者の負担を軽減し、GAP認証の取得に向けた改善活動を促進します。
産業機械メーカー大手の株式会社クボタの「KSAS(クボタスマートアグリシステム)」もGAP取得に役立つデジタル技術です。KSASは、圃場の管理や作業記録を電子地図で「見える化」し、作業進捗を把握することができます。農薬使用記録や圃場のリスク管理も簡単に行え、GAPに必要な書類やデータの作成をサポートします。KSASは、グローバルGAP以外にも、さまざまなGAP規格に対応しており、認証取得を支援する強力なツールです。
日本産ブランドを守るデジタル技術
最後にご紹介するのは、日本産農作物のブランド価値を守るためのデジタル技術です。
近年、課題として浮上しているのが海外市場での模造品や不正流通への対策です。日本流通管理支援機構はこれらの問題に対して、技術を駆使し、農作物のブランド保護を強化しています。
日本流通管理支援機構は偽造防止技術「Hidden Tag」搭載のセキュリティタグを使用したシールを作成し、日本産果実に貼付することで、産地や製品の正当性を証明し、消費者に信頼を提供しています。この技術は、QRコードを通じて消費者に産地や生産者の情報を伝え、日本産であることを証明するだけでなく、産地の情報提供によるPRも可能になるといったマーケティング活動にも役立っており、販促コストの削減にもつながっています。
なお、日本流通管理支援機構は「産地の証印」というサービスを導入し、農作物の産地証明を科学的に行っています。このサービスでは、微量元素や同位体分析を活用して、農産物や海産物、酒、肉などの産地を畑や農場レベルで証明します。近年、日本ブランドの農作物の種や苗が国外に持ち出され、他の国で生産されたものが「日本産」として流通するという問題が存在しています。このサービスを用いると、土壌や水の影響を反映した特徴的な残留物を通じて、産地の特定が可能となり、日本産と同じ遺伝情報を持った「偽日本産」を区別することができます。
今後の日本産農作物のブランド保護において、この技術は不可欠なものといえます。日本産ブランドの価値を守り、国際市場での競争力を高めるために、これらのデジタル技術や科学的分析は今後ますます重要な役割を果たすのではないでしょうか。
参考文献
- 八木宏典『図解知識ゼロからの現代農業入門』(家の光協会、2019年)
- 事業構想大学院大学出版部編「月刊事業構想2024年7月号『一次産業のDXで農・林・水産の新事業』 」(事業構想大学院大学出版部、2024年)
参照サイト
- 日本の農家が海外に進出するための戦略とは – slowbase
- 日本農業が青森県産りんごの製造体制を拡大!オランダ・GREEFA社製の大型選果機導入で約2.5倍の選果量を目指す 青森県弘前市のりんご選果場で9月下旬より稼働開始
- 東京都GAP|食の安全・安心
- 初めての方へ|クボタ営農支援システムKSAS
- 「GAP」取り組みをお考えの皆様へ|お役立ちツール|営農情報
- グローバルGAP、有機JASの認証にKSASを活用。|機能紹介
- グローバルGAPの取得の必要性とメリットとは?
- Hidden Tag
- 国内唯一の“科学的”原産地証明「産地の証印™」サービス開始 日本産ブランドの指紋情報をデジタル化し、産地偽装を防止・検証 | 日本流通管理支援機構株式会社のプレスリリース