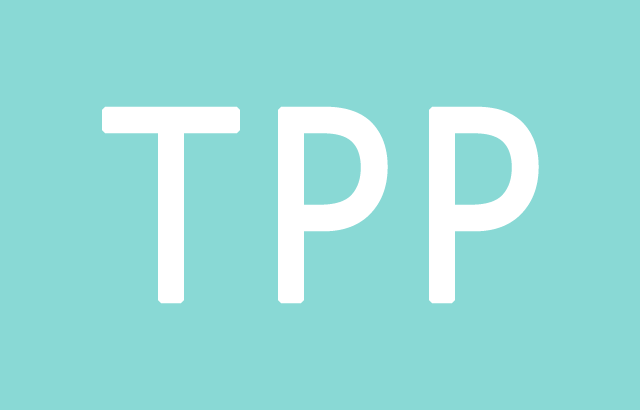日本の農業は、農家人口の減少と高齢化が進んでおり、2010年の約650万人から2018年には約419万人に減少しました。特に農業従事者の6割が65歳以上で、農地の集約化や農業の大規模化が進んでいます。
一方で、都市住民の農業や農村への関心が高まり、若者や定年退職者が農業に従事する事例が増えています。これらの新規就農者は、土地探しや資金調達の壁を乗り越え、農業経営を目指しています。
そこで本記事では、新規就農までの流れについて着目し、就農に向けてやっておきたい事前準備について紹介していきます。
主流は「親元就農」


新規自営農業就農者の大多数は「親元就農」が主な就農ルートとなっています。
親元就農は、農業を家業として受け継ぐ形態です。親元就農は依然として最大の就農ルートとして重要な位置を占めていますが、親元就農の割合は減少しつつあります。たとえば2000年代には、新規自営就農者の約8割が親元就農者でしたが、2010年代に入ると、雇用就農者の増加に伴い、7割台に減少しています。
また近年は、定年退職後に故郷に戻り、農業に従事する「定年帰農者」も増加しています。定年帰農者は、年齢的に50歳以上の人々が多く、定年後に実家の農業を引き継ぐケースが一般的です。
そのほか、親の経営を積極的に継承しようとする若年層も増えています。特に学卒や39歳以下の若者たちは、農業法人などでの勤務経験を経て、親の経営を引き継ぐケースが多くみられます。
実家が農家でない場合
主な就農ルートは「親元就農」と紹介しましたが、すべての新規就農者の家業が農業というわけではありません。
実家が農家でない人が新規に就農する場合には、いくつかの選択肢が存在します。主なケースにはこのようなものが挙げられます。
- 自分で農地や資金などを準備して独立する
- 自治体の支援制度を活用して就農する
- 農業法人に従業員として就職する
- 後継者のいない農家の経営を引き継ぐ など
ただし、いずれの選択肢を選ぶ場合においても、農業で生計を立てるためには事前の準備と慎重な計画が欠かせません。
新規就農に向けた事前準備


「令和3年度新規就農者(新規参入者)の就農実態に関する調査結果」によると、新機就農者が就農時に苦労した点は以下の順に割合が高くなっているとあります。
- 農地の確保
- 営農技術の習得
- 住宅の確保
とはいえ、まずは情報収集
就農時に苦労した点として、就農段階初期に行われる「相談窓口さがし」などの回答割合は比較的低かったと記されているものの、まずは情報収集が欠かせません。
全国新規就農相談センターや、各地で開催される「新農業人フェア」などのイベントに参加することで、有益な情報を得ることができます。
また、実際に「体験」して学ぶ方法も有効です。
たとえば茨城県にある日本農業実践学園では、農業未経験者向けに3日から3ヶ月の農業体験・研修を提供しています。そのほか、各地の農業大学校や民間の農業教育機関でも、土日や夏休みを利用した基礎的な農業技術の体験機会を設けています。農業法人で作業体験ができる農業インターンシップ制度もおすすめです。
前述した調査結果によれば、「(就農)地域の選択」「農地の確保」「資金の確保」といった情報収集元として、以下の順で割合が高くなっています。
「地域の選択」
- 親や兄弟、親類、知人
- 市町村
- 都道府県段階の就農相談窓口
- 研修先
「農地の確保」
- 市町村
- 親や兄弟、親類、知人
- 研修先
- 農業委員会
- 一般農家・農業法人
「資金の確保」
- 日本政策金融公庫
- 市町村
- 農協
- 農業普及指導センター
なお、書籍や雑誌、インターネットなども情報源としてあげられます。ただし、文字情報だけで農業の実態をつかむのは難しいといえます。各自治体の相談窓口やイベントに自ら足を運んだり、農業インターンシップなどを通じて自ら体験したりすることをおすすめします。
研修を受け、技術を得る
多くの人は1〜2年程度の本格的な研修を受けて、技術や経営ノウハウを学びます。研修には、自治体の制度を活用したり、先述した農業大学校や民間の研修機関に通ったり、といった方法があります。
研修を受ける際、事前にさまざまな研修先を比較検討し、研修中や研修後に考えられるメリットや難点を考慮してから研修先を選ぶことをおすすめします。
たとえば農業大学校や民間の研修機関に通う場合、専用のカリキュラムに沿った授業を受けながら技術を習得できますが、授業料や寮費がかかる点を考慮する必要があります。
農地と資金の準備
新規就農を目指す人は、研修を受けながら独立に向けての準備も進めることになります。農地や資金の準備は就農において重要なポイントです。
自治体の研修制度を利用している場合、農地の斡旋や独立後の支援を受けられることが一般的です。農業大学校では、研修後に農地を探すために自分で積極的に行動する必要があります。農地の購入や賃借には、市町村の農業委員会の許可が必要なこともあり、助言を得ながら慎重に進めることが求められます。
また、農業を始めるためには営農資金と生活資金が必要です。営農資金には機械や施設の購入費用や農作物に必要な資材が含まれ、生活資金は日々の生活費に充てられます。
営農資金を借りるためには、「就農支援資金」や「農業近代化資金」を活用できますが、これらは都道府県知事からの認定を受けた「認定就農者」に対して提供されるため、就農計画を作成し、認定を受けることが必要です。認定を受けると、無利子の支援資金を受け取ることができ、就農に必要な資金を確保しやすくなります。
就農後に活用したい支援策


多くの新規就農者が農業の厳しさに直面します。
技術面では、技術が未熟なために作業の段取りがうまくいかなかったり、収穫量が予定通りに確保できなかったりと、初年度は苦労が多くなるはずです。経営面では資金不足があげられます。
「令和3年度新規就農者(新規参入者)の就農実態に関する調査結果」によると、就農1年目に要した営農面での費用は平均で755万円、一方自己資金は281万円でした(差額474万円)。そして生活面での費用は170万円、就農1年目の農産物売上高は343万円です。
なお、上記調査結果では、前回の調査に比べ、営農面での自己資金、生活面での自己資金、就農1年目の農産物売上高のいずれも高い金額となっていると述べた上で、それ以上に費用合計が増加していることを指摘しています。多くの作目で費用合計が上昇しているうえ、就農1年目は赤字が生じやすいことが示されています。
そんな中、新規就農者の支援が強化され、各地で多様な支援策が展開されています。
「農業次世代人材投資資金」は、若手就農者の定着を目的とした支援制度で、就農前の研修や就農直後の安定しない時期に対して年間150万円の給付が行われます。
また地域独自の支援制度もあります。たとえば静岡県の新規就農支援事業に「がんばる新農業人支援事業」があります。この制度では、新規就農希望者が指導農家のもとで1年間、栽培技術や農業経営を学ぶことができるうえ、加えて静岡県や市町、JAや指導農家が新規就農者の「農地や資金の確保」「営農技術の習得」を全面的にバックアップするというものです。公式サイトによれば、平成16年以降、これまで200名以上が県内で新規就農を行い、98%という高い定着率を誇っています。
支援体制は地域ごとに異なりますが、自分が住んでいる自治体や就農を希望するエリアの自治体の支援制度をぜひ確認してみてください。
参考文献
- 堀口健治編著他『就農への道: 多様な選択と定着への支援』(農山漁村文化協会、2019年)
- 八木宏典『図解知識ゼロからの現代農業入門』(家の光協会、2019年)
- 中村恵二 『図解入門業界研究 最新農業の動向としくみがよ~くわかる本』(秀和システム、2023年)
参照サイト