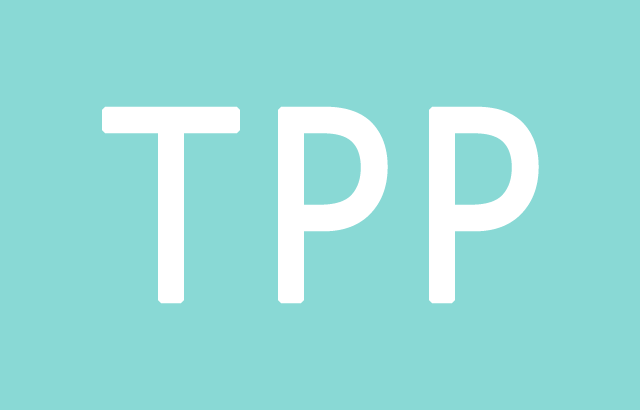2024年2月22日、農林水産省は「農業DX構想2.0」を発表しました。これは2021年3月に発表された「農業DX構想」を、その後のデジタル化の進捗状況や社会状況の変化、新たなデジタル技術の登場と発展を踏まえて更新したものです。
農業DX構想が示す未来図


「農業DX構想2.0」は、農業と食産業の未来像を描き、デジタル技術の活用がどのように社会に変革をもたらすかを示しています。
農業DX構想が進むことで、次のような未来が期待されています。
省人化と効率化
高齢化社会に対応するため、省人化技術の導入が進みます。労働力不足を解消し、作業効率を向上させる技術には、収穫ロボットや自動運転トラクターなどがあげられます。物流分野においては、トラック予約システムやRFID※を用いた検品作業の自動化が進行中です。
そのほか、農業のデータがスマート農業機械やアプリによって収集、生成AIによる解析が行われることで、生産面では農作業の効率化や作物の品質向上が進み、安定した食料供給の実現につながったり、経営面では精度の高い経営判断が行われることで農業者の経営安定につながったりといった事例が期待されます。
また農業従事者が少ない労力でデータ入力を行い、経営状況を管理する環境が整うことで、若者の農業への参入しやすさにつながり、農業の担い手が増加することも期待されています。
※RFID:Radio Frequency Identificationとは、電波や電磁波を利用して、ICタグなどの記録媒体の情報を非接触で読み書きするシステム。無線通信によって一定範囲内の複数のタグを一括で読み取ることができ、バーコードや2次元コードと比べて作業効率が向上する。
環境負荷の軽減
AIを活用した病害虫予測や精密農業技術により、化学農薬や肥料の使用量が最適化され、環境への負担が軽減されます。たとえば、AI診断アプリによる病害虫の早期発見や、スマートグリーンハウスでの最適な温度・湿度管理があげられます。
データドリブン経営の普及
データドリブン(Data Driven)とは、売上データやマーケティングデータなど収集したデータに基づいて判断したり、行動を起こしたりする手法です。経営・生産管理システムや農業データ連携基盤(WAGRI、気象や農地、収量予測など農業に役立つデータやプログラムを提供する公的なクラウドサービス)を活用することで、データに基づく意思決定が可能になります。これにより、適切な肥料や農薬の使用、効率的な収穫時期の選定が実現します。
地域経済の活性化
デジタル技術を活用した新たなビジネスモデルが誕生し、地域の雇用創出や農産物の付加価値向上が期待されます。
この構想では、農業が「儲かる産業」となり、より多くの人々が関わることで、食卓に新鮮で地域ごとの特色が生かされた食材を提供する社会が実現されることを目指しています。
農業DX取組の具体例


農業DXは、農業の生産性向上や効率化、品質改善を目指し、デジタル技術の導入を進めています。前述で「農業DX構想が示す未来図」と紹介しましたが、デジタル技術を導入した農業経営の取り組みはすでに実践されているものも多々あります。
以下では、いくつかの実例をご紹介します。
ドローンによる農薬散布
農業分野に導入されるデジタル技術の中で、よく目にする事例かもしれません。ドローンを利用した農薬散布は省力化と効率化を実現します。たとえば、ドローンとデータ解析を組み合わせて必要な場所にだけ農薬を散布することで、農薬使用量とコストの削減、作業時間の短縮につながります。また散布の際、作業員の被ばくリスクを減らせることもあり、安全性の向上にもつながっています。
データ活用による生産管理・品質向上
データを活用し、農作物の生育環境を最適化する取り組みもよく目にする事例かと思います。温度、湿度、日射量などのデータを解析し、作物の栽培方法の改善につなげます。トマト農家の事例などでは、データを基に水分量を調整し、糖度の高いトマトの生産に成功したといった報告が度々見受けられます。
ロボットによる農作業自動化
AIを搭載したロボットによる農作業の自動化が進んでいます。さまざまな企業が自動収穫ロボットの開発に取り組んでいます。このような技術革新は、農作業の効率を飛躍的に向上させることが期待されます。
農作物のD2C販売
D2C(Direct to Consumer)販売は、農家が消費者と直接取引を行う仕組みです。仲介業者を介さずに新鮮な農作物を提供することができるため、農家は利益率を向上させると同時にブランド力の強化が可能になります。有名な専用プラットフォームとして「食べチョク」などのサービスが知られています。一般の農家でもオンラインで比較的簡単に販売できる環境が整っています。
デジタルツールを活用した青果流通
前述したように、物流分野において、トラック予約システムやRFIDを用いた検品作業の自動化が進行しています。デジタルツールの活用が新しい青果流通の仕組みを作り出しています。たとえば静岡県卸売青果市場を中心に、野菜の卸売を行う東海青果株式会社が活用する「やさいバス」がその一例です。
「やさいバス」は、農家と消費者をデジタルでつなぐ新しい流通システムです。農家はオンラインで消費者から直接注文を受けます。農家は商品を指定の場所(JA施設や青果店など)に届け、持ち込まれた野菜は専用の冷蔵トラックで当日中に購入者に配送されます。
このシステムでは、受発注の記録が流通の過程で自動的に残ります。そのため、伝票を書いたり集計したりする手間がありません。効率化を実現したこの取り組みは、農業従事者と消費者の双方に利便性を提供しています。
課題も残っている


高齢化や農業の担い手不足といった課題、新たなデジタル技術の登場・発展といった社会状況の変化に対応する上で、農業DXの推進は必要不可欠といえますが、課題も残っています。
まず、デジタル人材の確保が難しいという点があげられます。最新技術を使いこなせるエンジニアやビジネス戦略とデジタル活用の両方に精通した人材の不足が課題となっており、長期的に人材育成に注力する必要があります。
次に、初期費用やランニングコストがかかる点について。農業DXでは、大規模な生産プロセスの変革が求められるため、多額の投資が必要となります。事業者が農業DXを積極的に進めたいと考えていたとしても、事業者の規模によっては、導入費用や手間の問題でスムーズにDX化を進められない場合もあります。この課題に対しては、公的な支援が欠かせません。
農業DX構想の今後
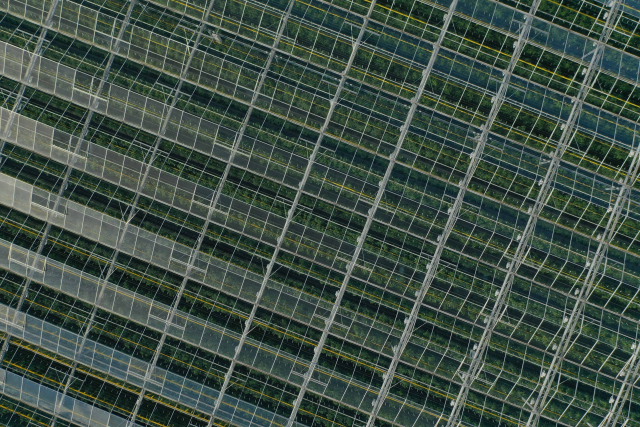
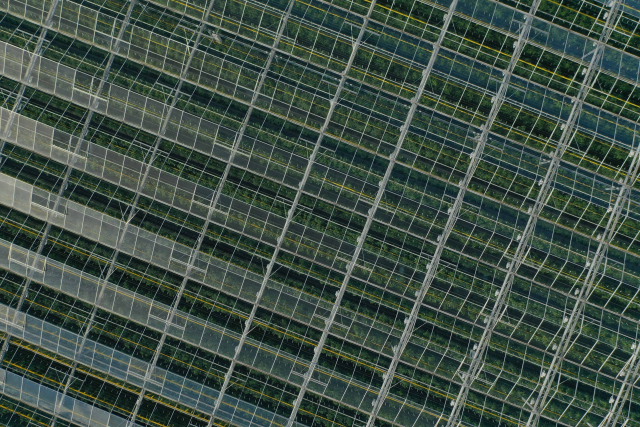
新たなデジタル技術の登場と発展は今もなお続いています。そのため、農林水産省は2026年初頭をめどに同構想を見直す予定としています。
2021年3月に発表された「農業DX構想」、2024年2月に発表された「農業DX構想2.0」から、内容がさらに発展することが見込まれます。社会情勢も日々変化しており、新たな課題も登場するかと思いますが、農業と食産業の未来像がどのようなものになり、どう実現していくのか気になるところです。
参考文献:事業構想大学院大学出版部編「月刊事業構想2024年7月号『一次産業のDXで農・林・水産の新事業』 」(事業構想大学院大学出版部、2024年)
参照サイト
- 農業DX構想 2.0
- 【農村でも進むDX 】デジタル田園都市国家構想の取り組み事例を紹介 – Labid Journal
- 農水省 「農業DX構想2.0」とりまとめ、未来予想図を提示 | ニュース 2024年 2月
- 農業DXとは?現状と課題、3大メリット、最新事例5選も紹介 – DX総研|DXの企画・開発・運用を一気通貫で支援
関連記事