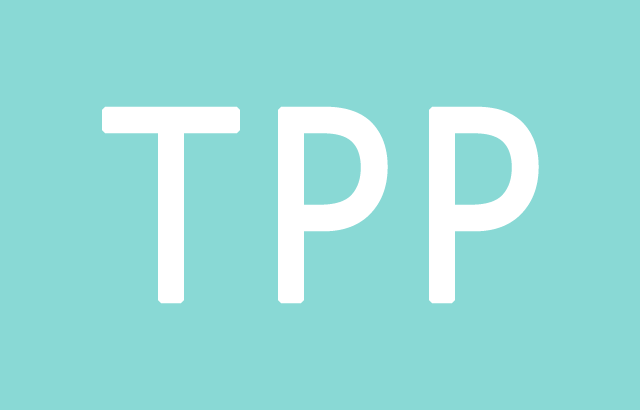近年、「働く女性」の話題が目にとまるようになりました。
社会における女性の活躍は、都市部に限ったことではありません。農業においても、女性の働き方が注目されています。
農林水産省は、女性農業者を対象にした「農業女性プロジェクト」を掲げています。本記事では、農業従事者の減少、高齢化に対する対策のひとつとして掲げられているこのプロジェクトについて紹介します。
農業女子プロジェクトとは
2013年11月、農林水産省を事務局に始まったプロジェクトです。当初は、37名の女性農業者、9社の民間企業が集まり、プロジェクトが開始されました。このプロジェクトは「女性目線」をフルに活かしたプロジェクトです。生活や仕事、自然と関わる中で得た知恵を、技術やノウハウ、新しい商品やサービス、情報に活かし、発信するのが狙いです。また「農業女子プロジェクト」として外へ発信することで、農業に興味関心を抱く女性を増やし、女性農業化の増加を図っています。
「農業女子プロジェクト」公式サイトにて掲げられている「目的」の欄を見ると(一部抜粋)、
生産力
農業女子の生産力の可能性を拡げる
(生産物の売り場企画、自社サービスに農関連サービスを取り込むなど)
知恵力
農業女子ならではの知恵を商品化する
(農業女子の知恵を活かした商品/サービス/情報開発、農業女子の知恵を活かした既存商品等の改良など)
市場力
農業女子という新市場をつくる
(不満を解消する商品改良、欲求を満たす商品開発)
と挙げられています。「女性目線」に立った商品開発、生産効率の向上をはかれば、今まで見逃していた着目点が見つかるかもしれません。「農業女子」というジャンルが、従来の農業を変えていく事が期待できます。また「農業女子プロジェクト」は女性農業家が対象ですが、ここで掲げられている目的は、生業として向き合うのに重要な「経営面」を学ぶことができ、男女問わず学んでおきたい内容だと言えます。
本記事の最後には、女性農業家の事例についてもご紹介しますよ!
農業と女性の関わり

女性は、農業の6次産業化等の担い手としても期待されています。
農林水産省の「農林業センサス」によると、1995年に414万人だった農業従事者の数は、2015年には209万7千人に減少したとあります。70歳以上の農業者が全体の約47%を占め、高齢化が顕著に現れています。そんな中、農業就業人口の約半数は女性です。時代背景も関係していると思われますが、50~64歳では男性を上回る数の女性が農業に携わっています。
しかし、49歳以下の女性の割合は10%と低いのが現状。農業の担い手として期待が高まっているにも関わらず、若手かつ女性の農業従事者はまだまだ足りていないのです。一部の農村では、まだまだ性差意識が強いのも実情です。
この現状を打破するためには、経営や農業発展への問題意識をもつ女性に向けて「人材育成」や「労働環境の改善」「セミナーの開催」「ロールモデルの情報発信」などが必要と言えます。もちろん当事者のみならず、地域のコミュニティに対する働き方も必要でしょう。どんなに人材育成で優秀な女性農業家が現れても、コミュニティがそれを良しと思わず、活躍の場を阻害してしまっては意味がありません。
女性農業家が抱える課題

こればかりは女性ならではの悩みと言いますか、ワークライフバランスに対する悩みや課題が目に入ります。農林水産省は平成24年度に「女性の農業への関わり方に関するアンケート調査」を実施しています。
そこで挙げられた「生活上の課題」には、「家事・育児との両立」「プライベート時間の確保」が上位に食い込んでいます。これらの観点から考えると、どうしても農業という生業は柔軟な働き方へは結びつかないように感じるかもしれません。自然のものを取り扱う生業ですから、農作物の状態や天候に左右され、予測できないライフイベントに対応できない可能性は高まります。
しかしこれらの解決策として「スマート農業」の活用が役に立つかもしれません。スマート農業とは、IoTやAI技術などを駆使して行う農業です。現在「収穫ロボット」「環境管理センサー」「農業用ドローン」など、さまざまな技術が登場しています。もし、これら技術が発展し、人が作業せずとも農作物が育てられるようになるとすれば、「家事・育児との両立」や「プライベート時間の確保」が可能になるのではないでしょうか。
女性農業家の事例
最後に、女性農業家の事例についてご紹介します。
宮崎県にあるおがわ農園の小川紘未(おがわ ひろみ)さんは、樹上完熟ミニトマトの栽培を行っています。彼女は6次産業化にも積極的です。トマトを使ったさまざまな加工品を開発し、販売しています。「女性目線」が活かされているのは、その商品パッケージです。通常、加工食品の瓶にはラベルが貼られていますが、彼女はラベルを貼りませんでした。理由は「食べ終わった後の瓶を再利用しやすくするため」。
この発想は、瓶を再利用し他の調味料入れなどに使った経験のある女性にしか思い浮かばないアイデアなのではないでしょうか。彼女は「農場女子プロジェクト」での活動も経験しています。
沖縄県の株式会社今帰仁ざまみファームで、座間味久美子(ざまみ くみこ)さんは沖縄伝統野菜・クワンソウの生産・加工・販売を行っています。商品パッケージデザインの一部を自分たちで行うなど精力的に活動する彼女ですが、中でもとてもユニークな試みがあります。それは畑のクワンソウが花を咲かせる時期に「花摘みバスツアー」を行っているということ。旅行会社との提携し、「農業×観光」をつなげ合わせた人物です。
「女性〇〇」という名称がなくなり、性別の垣根なく農業に取り組めるようになることが、女性の活躍の最終地点のようにも思えます。でも今は「農業女子プロジェクト」が継続し、農業従事者の増加につながることを期待しましょう。