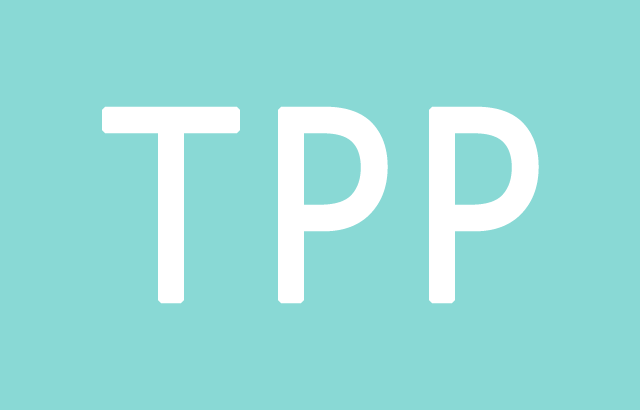雑草は水田や畑、草地、芝地のほか、庭園や休耕地など農耕地以外でも発生するため、一言で定義するのが難しい存在ですが、作物生産の観点から定義すると、「雑草」は作物に対してさまざまな被害を及ぼし、生産に有害な植物を指します。
本記事では農地によく現れる代表的な雑草と、それらによってもたらされる雑草害についてご紹介していきます。
水田に現れる代表的な雑草


水田に現れる代表的な雑草には以下のものがあげられます。
<一年生雑草>
- イネ科(タイヌビエ、ヒメタイヌビエなど)
- カヤグリグサ科(タマガヤツリ、ヒナガヤツリなど)
- ミズアオイ科(コナギなど)
- ゴマノハグサ科(アゼナなど)
- ミソハギ科(キカシグサなど)他
<多年生雑草>
- イネ科(キシュウスズメノヒエ、チクゴスズメノヒエ、アシカキなど)
- カヤグリグサ科(イヌホタルイ、ミズガヤツリ、クログワイなど)
- オモダカ科(ウリカワ、オモダカ、ヘラオモダカなど)
- ヒルムシロ科(ヒルムシロなど)他
なお、一年生雑草は毎年新しい種子から発生する雑草を指します。一方、多年生雑草は秋冬や夏の高温時に地上部が枯れても、地下部の根茎や塊茎などは生存して残り、そこからまた成長するものを指します。
畑に現れる代表的な雑草


畑に現れる代表的な雑草には以下のものがあげられます。
<一年生雑草>
- イネ科(メヒシバ、ヒメイヌビエなど)
- アカザ科(シロザなど)
- タデ科(オオイヌタデなど)
- ヒユ科(イヌビユなど)
- スベリヒユ科(スベリヒユなど)他
<多年生雑草>
- イネ科(チガヤなど)
- カヤツリグサ科(ハマスゲなど)
- トクサ科(スギナなど)
- キク科(セイダカアワダチソウなど)他
JA全農が公開する雑草図鑑が便利
JA全農が公開するウェブサイト「JA全農提供 雑草図鑑」には、水田、畑地、樹園地に発生する代表的な雑草が掲載されています。このサイトの便利なところは、「雑草の形」から雑草の種類を検索できるところです。
たとえば水田雑草の場合、まずはじめに「広葉雑草」、「イネ科」、「カヤツリグサ科」、「ウキクサ・藻類」の4種類から該当するとされる雑草のタイプを選ぶ必要はあるものの、「イネ科」、「カヤツリグサ科」、「ウキクサ・藻類」を選んだ場合には、すぐに該当するとされる雑草の画像が出てきます。
また「広葉雑草」の場合には、茎や葉の特徴から雑草のタイプを判別するページが続き、そこから代表的な雑草の画像を見ることができます。
雑草害の程度について


雑草は養分や水分の摂取において作物と競合します。雑草と競合することで、作物の養分や水分の吸収量が不足すると、作物の生長に悪影響が及びます。また雑草が繁茂することで作物の受光量が減ると、穂や子実が小さくなってしまううえ、風通しが悪くなれば病害虫の発生にもつながります。
草丈が小さかったり、初期生育が遅かったりする作物は雑草害を受けやすいので、雑草の防除によりいっそう注意が必要になります。また施肥方法にも注意が必要です。全面全層施肥を行うと、畔間の雑草の生育も旺盛となるため、放任してしまうとあっという間に雑草が繁茂してしまいます。
なお、雑草の発生率と作物の減収率には相関があり、仮に雑草を放任した場合、水稲では以下のような減収率となります。
- 一年生の小型雑草によって15〜20%の減収
- イネ科のノビエなどが多量に発生した場合、40%以上の減収
- 多年生の小型雑草によって15〜20%の減収
- カヤグリグサ科のミズガヤツリで30〜50%の減収
また畑作物の場合、イネ科のメヒシバによる雑草害により、トウモロコシでは10%程度の減収となりますが、大豆は60%、落花生では90%以上の減収となります。
雑草との向き合い方


一般的な雑草の防除方法には除草剤の利用があげられます。ただし、近年では薬剤抵抗性をもった雑草が出現し問題となっています。たとえば日本では、ヒメタイヌビエやアゼナにスルホニルウレア系除草剤への抵抗性が報告されています。
また東邦大学の研究によると、世界中で用いられている除草剤・グリホサート剤に対する抵抗性をもった雑草「オオホナガアオゲイトウ」が外来雑草として定着したことを報告しています。
2005年にアメリカのジョージア州で発見されたその雑草は、全米中に急速に蔓延して難防除性雑草となっただけでなく、日本の主要な穀物輸入湾港から移入したとあります。
害虫であれ、病原菌であれ、雑草であれ、薬剤を使用する対象に抵抗性や耐性を獲得させないためにも、以下のことが重要です。
- 同じ作用機構の薬剤の使用回数を制限する
- 作用機構の異なる薬剤をローテーションで使用する
- 作用機構の異なる薬剤との混合剤を使用する
また本サイトでは、雑草との向き合い方として、以下のような記事を紹介しています。こちらも合わせてご覧ください。
参考文献:日本植物防疫協会編『農薬概説2021』(日本植物防疫協会、2021年)
参照サイト
- 雑草解説(稲作) – 宮城県公式ウェブサイト
- (2)雑草の生育時期と繁殖生態
- (3)雑草害と防除適期
- 病害虫や雑草の害を受けると、農作物の品質にどのような影響があるのでしょうか。|農薬は本当に必要?|教えて!農薬Q&A|JCPA農薬工業会
- 日本における除草剤抵抗性雑草の出現と 除草剤の開発
- 除草剤抵抗性雑草の出現と移入 | 生物学科 | 東邦大学
- 農薬を使い続けると、害虫、病原菌や雑草に対して防除効果がなくなることがあるのでしょうか。|農薬はどうして効くの?|教えて!農薬Q&A|JCPA農薬工業会
(2024年5月22日閲覧)