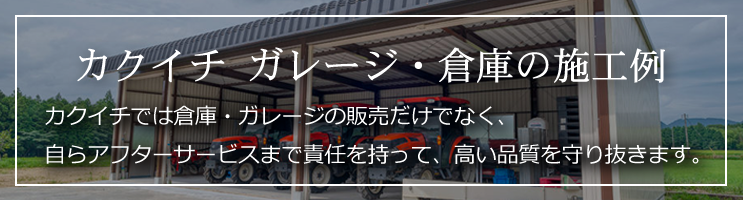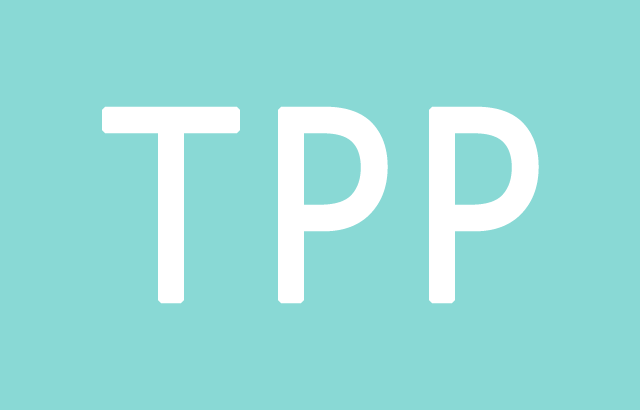農業における厄介なトラブルには「病害虫による被害」が挙げられるのではないでしょうか。特に病害菌による被害は蔓延のスピードが早く、広い範囲で農作物が影響を受けるだけでなく、枯死に至るケースも少なくありません。農作物が枯れてしまっては、生業として大打撃です。
そんな病害菌の中でも有名かつ甚大な被害をもたらすものに「稲いもち病」が挙げられます。稲いもち病は品種に対する病原性が異なる特徴があります。また菌の変異が起これば、これまで耐性があった植物にも影響を及ぼすため、脅威とも言えるでしょう。そこで本記事では稲いもち病の脅威を振り返ると共に、現在研究が進められている「稲いもち病を抑制できる新たな抗菌物質」について紹介します。
稲いもち病の脅威について

いもち病とは、Pricularia oryzaeと呼ばれる糸状菌が原因菌です。
稲に感染するものを「稲いもち病」と呼んでいますが、感染は稲に限りません。
ササやタケにも感染することがあります。稲いもち病という名称で呼ばれていますが、農業においては症状が発生する部位によって異なる呼び方をしています。
葉に発生するいもち病は「葉いもち」、穂に発生するいもち病は「穂いもち」と呼ばれます。「穂いもち」の分類はさらに細かく「穂首いもち」「枝梗いもち」「もみいもち」などと呼ばれます。病原菌は同じものですが、その症状は違いが生じます。いもち病の恐ろしさは、蔓延するところにあります。糸状菌の胞子によって伝染しますから、いもち病を発生させないためには、まず大前提として原因菌を植物に侵入させないことが重要となるのです。胞子は風などで遠くから飛来することもあります。稲いもち病が蔓延するのに最適な条件が整い次第、稲に対して悪さを働きます。
<葉いもちについて>
葉いもちにかかると、2種類の病斑が見られます。
「湿潤型病斑」は、円形~楕円形の灰緑色~暗緑色の病斑ができるのが特徴です。もっとも伝染力の強い病斑と言われています。
「止まり型病斑」は「湿潤型病斑」から移行したものです。中央部が灰白色、褐色紡錘形の病斑です。
<穂いもちについて>
穂いもちは発生すると、収量や品質低下を招きます。農作物の生産に大きく影響する病害のため、十分な注意が必要になります。
「穂首いもち」による影響は、出穂した時期によって異なりますが、いずれも生産に影響します。出穂初期に病気にかかると、水分の供給が断たれてしまい、穂が白くなってしまいます。出穂中~後期に感染すると、実りが極端に悪くなります。
「枝梗いもち」が進むと、枝梗節から穂軸節や穂首節へと病斑が進み、灰白色となった穂は折れやすくなります。
「節いもち」では葉節部に感染が見られます。病班は黒く凹んだようになり、スポンジ状になっていきます。こうなると、穂は折れて倒伏しやすくなってしまいます。
「籾いもち」稲の成長の早い段階で感染すると、色は蒼白色になり枯死につながります。生育後期に感染しても、その影響力は絶大です。不完全米の増加を招くため、コメの生産を生業とする人において絶対に起きてほしくない病気だということが分かります。
<発生原因について>
それぞれの発生部位に対して、細かく原因はありますが、端的に説明すると「温度・湿度」などが主な原因です。20~25℃という温度は、病原菌の活動が活発になる温度です。
それに加え、湿度が90%を超えると、胞子の飛散が活発になります。胞子が発芽するのに必要な水分も得やすいため、雨の降る時期は要注意です。
また稲自身の強さに対する影響もあります。稲は成長するに連れて、病害への抵抗を高めていきますが、「日照不足」がその性質を阻害します。日照不足が続き、抵抗力の少ない状態の稲に対し、病害菌は侵入を進めていきます。過度な追肥も稲の抵抗力を弱める原因です。稲自身の抵抗力を阻害するような行動を誤ってとってしまうと、稲いもち病のかかりやすさもアップすると考えて良いでしょう。
<防除方法>
「いもち病」が発生しやすい時期の情報を利用し、最適な時期にあらかじめ薬剤散布を行うことで予防を行うことが一般的です。近年では、稲いもち病に対する抵抗をもった品種も数多く開発されていますが、抵抗品種に罹患できる菌の突然変異も起こるので油断できません。あらかじめ病気の発生要因を取り除くことが重要と言えます。
新たな抗菌物質

そんな中、鳥取大学などの研究グループが、稲いもち病の発生を抑える抗菌物質のメカニズムを明らかにしました。
稲は自ら防御機能を高めるために、ファイトアレキシンや植物ホルモンを増加させるのですが、食用きのこの廃菌床から得られた抽出物が、その抵抗性を誘導すると言うのです。それら抽出物を稲に噴霧すると、いもち病の軽減につながるということはすでに明らかにされていたようですが、研究チームがそのメカニズムを解明したのです。
乾燥したシイタケとブナシメジの廃菌床100gを使用。蒸留水1lを加え、120℃で15分熱処理して得られた抽出物を稲の幼苗に噴霧。2日後に原因菌を接種し、分析したところ、病原菌の抵抗に利用されるファイトアレキシンの蓄積が確認されています。植物ホルモンにおいては、イソペンテニルアデニンという物質の蓄積量が、何もしていない水稲と比べて約100倍になったとの報告があります。
またこの研究の魅力は、稲いもち病に対する新たな抗菌物質が見つかったことだけでなく、きのこの廃菌床を活用することで、「きのこと水稲双方の生産者のメリットになる」ということにあります。
病原菌のみならず、害虫や害獣による被害は毎年のように報告され、農業従事者の頭を悩ませます。しかし研究もまた、日々発展し続けています。最後に紹介した新たな抗菌物質や、耐性種などの存在が、今後の農業に大きく関わってくることでしょう。
なお稲いもち病の対策には、防除の基本「伝染元を断つ」が非常に重要です。いもち病の恐ろしいところはその感染力です。取り置きしてある苗や放置している籾殻に、すでに病気が蔓延しているかもしれません。感染が疑われる植物は即座に処分し、稲いもち病が活発化しないような環境、農薬散布などによる防除を徹底しましょう。