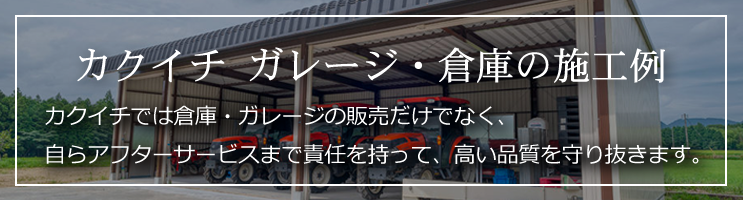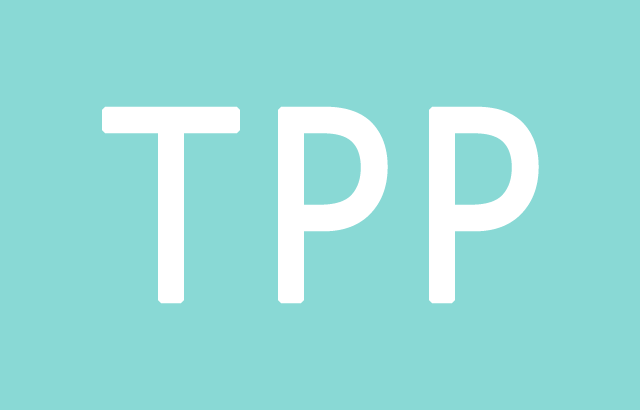環境への配慮や持続可能な農業のあり方が求められる現在、その取り組みの1つとして化学肥料の使用低減が掲げられているのを度々目にします。
しかし現代に至るまで、化学的に合成された肥料が開発・利用されてきたことを考えると、それら肥料・農薬による農業生産への恩恵に目を向けてみるのも1つの視点として重要ではないでしょうか。
そこで本記事では、化学肥料の意義と、どのような使い方が環境に影響を及ぼしてしまうのかについて紹介していきます。
化学肥料の使用を低減するうえでの課題


歴史的背景
産業革命後、ヨーロッパでは著しい人口増加に伴い、食料供給が不足していました。そのような背景の中、有機化学の確立に大きく貢献した化学者であるユストゥス・フォン・リービッヒが無機栄養説を発表したことで、肥料の製造が積極的に行われ、食糧増産につながりました。
使用低減の課題
リービッヒの発表により登場した化学肥料によって食糧危機が回避されましたが、現代においても全世界の人口は増加しており、未来に食糧危機が訪れる可能性がないとは言い切れません。
世界の人口は1950年には約25億人だったのが、2000年には約61億人に、2023年には約80億人となっています。2050年までには90億人を超えると予想されています。一方で、三枝正彦『循環型農業と最大効率最少汚染農業』(化学と生物 Vol.42 No.1、2004年)に記されているように、世界の耕地面積の年間増加率は1950年代から低下し、“これ以上耕地面積を増大することはきわめて難しくなっている”、とあります。
地球温暖化による異常気象や、発展途上国における食生活の欧米化などを考慮すると、食糧供給を維持する観点からは、単位面積あたりの穀物生産量を向上させる必要があります。一方で、現代で環境への配慮から求められる化学肥料を使わない農法や有機農業では、一般的に単位面積あたりの収量が減少するとされており、ジレンマが生じているのが現状です。
日本特有の難しさも
加えて日本の場合、高温多湿という夏季の気候条件で、認証を受ける有機農業を継続的に営農するのは難しいともいわれています。
また『循環型農業と最大効率最少汚染農業』では、こんな指摘もあります。
自給率がきわめて低い日本の農業では生物性有機廃棄物に由来する栄養分のすべてを農地で処理することは量的にも不可能
出典:三枝正彦『循環型農業と最大効率最少汚染農業』(化学と生物 Vol.42 No.1 p.23、2004年)
化学肥料の使用低減と環境保全の関係


江口定夫『窒素循環から見た健康な食と有機農業の密接な関係』(有機農業研究14(1)44-48、2022年)より、化学肥料の使用低減と環境保全の関係は視点によって変わることがわかります。
地球上の反応性窒素(大気の78%を占める安定した窒素ガスを除く窒素化合物の総称)をこれ以上増大させないためには、人為的に生成される反応性窒素を極力減らすこと、すでに地球上に存在する家畜糞尿や作物残渣、土壌有機物などに含まれる反応性窒素をいかに効率的に循環利用するかが求められます。
化学肥料を使わずに、堆肥やごく一部の微生物による生物学的窒素固定によって窒素源を有効活用する有機農業は、地球上の反応性窒素を増大させないという点では環境保全的な農業です。
しかし上記論文は、堆肥等を投入することで慣行農業よりも一酸化窒素(主要な温室効果ガスの1つ)の排出や硝酸態窒素(地下水汚染や人体への影響が懸念される)の溶脱が増大する場合には、有機農業=環境保全的とは言い難くなる、と指摘します。
加えて、冒頭でも紹介した通り、単位面積あたりの収穫量が慣行農業に比べて明らかに低下する場合には、人口を養うために多くの農地面積が必要になる、すなわち森林破壊の拡大へとつながり、同じく環境保全的とは言い難い、とあります。
化学か有機か、ではなく過剰施肥に問題がある
福嶋宏和『過剰な窒素肥料が及ぼす環境負荷の低減に向けて-地下水汚染と農作物中の硝酸塩の低減-』(科学技術動向 No.69、2006年)では、化学的に合成されたものか有機であるかではなく、過剰施肥が環境に大きな負荷を与えていることを記しています。
同記事によると、1994年に当時の総務庁が公表した「農業における環境保全対策に関する行政監督」にて、1990年度に調査地の半数で施肥基準を超える肥料が施用されていたことが記されています。この背景として、多くの農業者が農作物の収穫量をより高めるために過剰な施肥を行っていたことが考えられます。
農作物が必要とする窒素量を超えた窒素肥料が施されると、余剰分が地下に浸透することで地下水の汚染(硝酸性窒素濃度の上昇)につながり、また農作物の種類にもよりますが、多くの硝酸塩が作物中に蓄積されてしまいます。
硝酸塩自体は、通常量を摂取する程度であれば、ただちに人体に害を及ぼすものではありません。しかし体内で還元され、亜硝酸イオンに変化すると、全身に酸素不足が引き起こされる症状を及ぼすメトヘモグロビン血症や発ガン性物質であるニトロソ化合物の生成に関与するおそれが指摘されています。
今、取り組むべきこととは


化学肥料を用いるか、用いないか、有機農業を取り入れるか、取り入れないかというよりは、種々の農作物の成長段階に応じて、必要な時、必要な場所に、必要な量の肥料を与えることが重要だといえます。
もちろん生物由来の有機廃棄物を農地に還元して栄養成分を補給することは、環境保全における基本姿勢です。とはいえ、農業経営を持続することも忘れてはいけません。
『循環型農業と最大効率最少汚染農業』で著者はこう書いています。
一般に、「持続的農業=環境負荷軽減農業あるいは有機農業」と考えられがちであるが、その前に何よりも安定した農家経営が重要であり、農家経営の持続なくして持続的農業はあり得ない。
出典:三枝正彦『循環型農業と最大効率最少汚染農業』(化学と生物 Vol.42 No.1 p.23、2004年)
まずは作付する前に土壌に残存している窒素量を測定し、作付から収穫までの間は、物理的・化学的・生物学的防除などさまざまな防除方法を組み合わせて病害虫から植物を守りましょう。
養分が不足する場合には適正量の化学肥料で補うことも必要といえます。施肥を施す際はできる限り局所的に行い、化学肥料であろうと有機肥料であろうと硝酸塩の流亡量が少ない肥料を利用するよう心がけましょう。
生育途中の農作物の観察も欠かせません。過度に肥料を与えるのではなく、栄養診断を適宜行い、作物の栄養状態に合わせて施肥を行いましょう。
参考文献
- 江口定夫『窒素循環から見た健康な食と有機農業の密接な関係』(有機農業研究14(1)44-48、2022年)
- 福嶋宏和『過剰な窒素肥料が及ぼす環境負荷の低減に向けて-地下水汚染と農作物中の硝酸塩の低減-』(科学技術動向 No.69、2006年)
- 三枝正彦『循環型農業と最大効率最少汚染農業』(化学と生物 Vol.42 No.1 p.23、2004年)
参照サイト