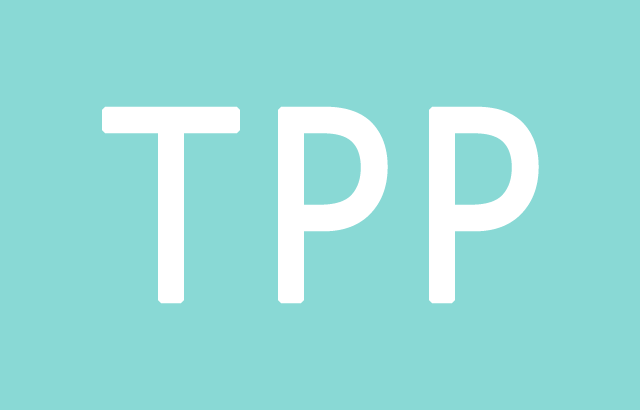2024年1月1日に公開された日本農業新聞の記事によると、レモンに国産志向が見られています。記事によれば、輸入品に比べて輸送時間が短く、収穫後の防カビ剤を使わない国産品は皮ごと食べられるという点が、安心感につながっています。そんな国産レモンは家庭用だけでなく、飲食店や加工向けなど幅広い用途で需要があります。
そこで本記事では、国産レモン栽培の基礎知識と題し、日本国内のレモンの需給状況や栽培に関する基礎知識についてご紹介していきます。
レモンの需給事情

2022年6月24日に公開された、農林水産省が運営するニッポンフードシフト公式noteによると、日本のレモン消費量は約5万トンであり、そのうち4.2万トンが輸入、0.8万トンが国産とあります。
海外産に依存している状況ではありますが、国内生産量は増加傾向にあります。たとえば、「現代農業 2023年11月号」に掲載された情報によると、1990年のレモン国内生産は、栽培面積が125ヘクタール、収穫量が2027トンでしたが、2000年代初頭より生産量が増加していき、2010年代初頭には栽培面積は500ヘクタール、収穫量は1万トンにまで増大しました。
主産地について
詳しくは後述しますが、レモンは寒さに弱く、潮風に強いという特徴があります。産地として古くから知られているのはイタリアのシチリア島などですが、生産量に特化して見てみると、インド、メキシコ、中国、アルゼンチン、ブラジルが上位を占めます。
また、日本の主な輸入国はアメリカで(生産量ランキングにおいては7〜8位あたり)、アメリカとチリの2カ国が輸入全体の80%以上を占めています。
国産レモンの主産地には広島県や愛媛県があげられます。レモンの基本的な栽培条件は、年平均気温が17度以上、最低気温がマイナス3度以上であることから、瀬戸内海島しょ部に産地が集中しています。また、そのほか、和歌山県や熊本県、神奈川県などでも一定の収穫量があります。
レモン栽培の基礎知識

まずは弱点を抑える
「主産地について」でも記した通り、レモンは寒さに弱いです。マイナス2〜3度が数時間続くと、果皮障害や枝の枯れ込み、花の減少といった被害が生じます。そのため、暖かい場所に植えること、幹にワラや不織布などを巻く、年内に収穫するなどの対策が必要です。
また風や乾燥も弱点です。
レモンは風に吹かれると落葉しやすい特徴があります。落葉してしまうと花が充実せず、樹勢の低下につながります。風の当たらない場所に植えるか、どうしても風が当たってしまう場合には、寒さに強い針葉樹コニファーなどをほ場のまわりに植えて防風垣を設けたり、防風ネットを設置したりといった対策を行います。
レモンは高温には強いものの乾燥には弱く、強い乾燥ストレスを受けると、葉の色が薄くなり、落葉してしまいます。乾燥によって生育が停滞してしまうことがあるので、植え付け後2ヶ月程度は1週間に1〜2回かん水を行います。その後も7〜10日以上雨が降らない場合にはかん水します。レモンが苦手とする季節である冬場のかん水も有効です。
レモンの病気で、乾燥ストレスで発生しやすいとされているのが「かいよう病」です。かいよう病は、葉や果実、枝に褐色の病斑を生じさせ、多発すると落葉を引き起こします。果実が風にすれて傷ついたり、新芽がミカンハモグリガなどにやられたりすると、その傷口が病気の発生源となります。
かいよう病の対策では、まず防風対策が重要です。また傷口を作る害虫の防除、伝染源を減らすために罹病した果実や枝は除去するなどの対策を行います。窒素など肥料のやりすぎにも注意してください。
レモンならではの特徴
レモンは他のカンキツ類に比べて、樹勢が旺盛なのが特徴です。枝がよく伸び、樹体が大きくなりやすい分、樹高が高くなりすぎたり、樹形が乱れたりしやすいため、芽かきや誘引などの処理が有効です。
レモンには四季咲き性(一定の開花期がなく、成熟した個体であれば開花条件が整うことで、季節に関係なく開花する性質)があり、ハウス栽培であればその性質を利用して夏に収穫することもできます(通常は5月に開花のピークを迎え、10月頃〜翌年の春までが収穫期)。
鉢植えと地植えでこんな違いが
必ずしも1年目から果実がつくわけではありませんが、鉢植えなら1年目で収穫できることがあります。小さめの鉢に植えることで根の生育が制限されると、樹が育つ栄養生長が抑制される代わりに、花や果実が成長する生殖生長に傾き、着果しやすくなるからです。
ただし、この場合、収穫後の樹を地植えすると、根の生育が制限されなくなるので栄養生長に傾き、花が咲かなくなったり、果実がついても生理落果しやすくなったり、その後数年は果実がならないこともあるので、その点は把握しておく必要があります。
一方、地植えは根も枝もよく伸びるので樹体が大きくなります。果実がなりだすのに時間がかかりますが、収穫量は増えます。
参考文献:農文協編『現代農業 2023年11月号 特集:レモンとユズと香酸カンキツ』(農山漁村文化協会、2023年)
参照サイト
- [農畜産物トレンド調査]野菜、果実の「ネクストヒット」はこれ! / 日本農業新聞
- 持続可能な国産レモン栽培への挑戦|ニッポンフードシフトの公式note
- 輸入レモンについて | 船昌商事株式会社
- 世界のレモン・ライム 生産量 国別ランキング・推移 – GLOBAL NOTE
- レモン 檸檬 れもん
- 病害虫図鑑 カンキツかいよう病 – あいち病害虫情報 – 愛知県
(2024年6月17日閲覧)