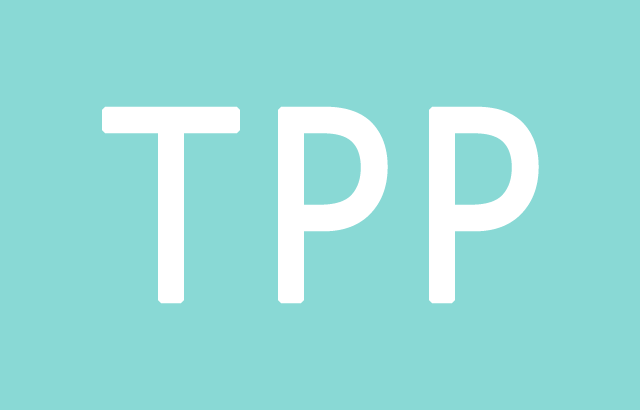糸状菌(カビ)による病害「萎凋病」についてまとめました。
萎凋病の症状と原因

“萎凋病”とつく病害には
- 萎凋病
- 根腐萎凋病
- 半身萎凋病
の3つが挙げられます。
それぞれの症状や原因について紹介していきます。
萎凋病
高温時に発生しやすい病気で、萎凋病になると生育が極端に遅れ、着果不良になります。
萎凋病になると、植物の下葉が日中はしおれ、夜間に戻る状態が繰り返されます。しおれは徐々に上葉や生長点に進んでいき、葉の色は黄色に変わっていきます。症状が進むと黄化し葉はやがて枯死していきます。
萎凋病の特徴には維管束の褐変が挙げられます。発病した株の茎を切断すると、地際部から葉が黄化した位置あたりの茎と葉柄の維管束が褐変しています。萎凋病末期になると根全体の維管束にも褐変が及びます。
病原菌は糸状菌のFusarium oxysporum Schlechtendahl:Fries f. sp. lycopersici(フザリウム・オキシスポラム・f.sp.リコペルシシ)です。発病適温は27〜28℃です。
この病原菌は萎凋病で枯死した植物体内で、劣悪な環境に耐え、長期間生存できる器官(厚膜胞子)を形成し、枯死した植物が腐敗した後も、土壌中で生存し続けます。厚膜胞子が存在する土壌に宿主となる新たな作物が栽培されると、厚膜胞子は発芽し、厚膜胞子近辺に到達した根に侵入します。
根腐萎凋病
萎凋病とは対照的に、根腐萎凋病は低温時や寡照環境で発生しやすく、根腐症状がひどいのが特徴です。
根腐萎凋病になると、植物の茎葉が日中はしおれ、夜間に戻る状態が繰り返されます。症状が進むと黄化し、枯死します。発病株の根では、発病初期は細根が褐変し、細根の付け根に黒褐色の病斑が形成されます。褐変は徐々に根全体に及び、症状がひどい場合には、主根から地際部の茎も黒褐変し、腐敗します。
根腐萎凋病になると茎の髄※が空洞化し、外から押すとへこむようになります。
※髄
植物の茎では維管束が円筒状に形成されているが、その内方、中心部にみられる柔組織を髄という。皮層の柔組織とは放射組織 (射出髄) によって連結している。木本植物ではこの部が貯蔵組織となるものが多い。草本植物のなかには茎の急激な生長により、この部が破壊されて髄腔となるものがある (例:イネ、タケ、トクサ) 。
出典元:ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
病原菌は糸状菌の Fusarium oxysporum Schlechtendahl:Fries f. sp. radicis lycopersici(フザリウム オキシスポラム f.sp.ラディシス-リコペルシシ)です。この病原菌の発育適温は28℃ですが、発病適温は萎凋病と違い、10~20℃と低いのが特徴です。
この病原菌もまた、萎凋病同様、枯死した植物体内に厚膜胞子を形成し、土壌中で生存し続けます。
半身萎凋病
低温時の発生が多く見られる病気で、“半身”の名の通り、発病初期は株の「片側」の葉全体が黄化し、しおれていきます。春先から夏にかけて、そして秋期に発生が多く見られます。
半身萎凋病になると、植物の下の小葉が部分的にしおれていきます。しおれは2〜3日ほどで止まり、そこから葉が段々と黄変していきます。黄変の流れが特徴的で、まず発病部がくさび形に黄白色から黄色になります。数日かけて小葉全体が黄変すると、最初に発病した部分から徐々に褐変していき、枯死します。
病勢の進展にともない、このような症状は次第に上位葉に進み、着果は不良となる。葉柄や茎の導管は褐変するが、萎凋病に比べると不明瞭である。
葉柄や茎を切断したときの褐変の色は、半身萎凋病の場合、萎凋病に比べて不明瞭で薄いです。
病原菌は糸状菌のVerticillium dahliae(バーティシリウム ダーリエ)です。トマトのみに病原性を示すものや、トマトやナス、ピーマンなどに病原性を示すものなど複数の系統が知られています。病原菌の生育適温は22〜25℃で、30℃でも生育します。発病適温は22〜24℃です。やや乾燥した、アルカリ性に近い土壌を好みます。
萎凋病、根腐萎凋病の病原菌である Fusarium属とは異なる器官ですが、土壌中で長期間生存するための休眠器官(微小菌核)を形成し、土壌中で10年以上生存するとされています。
萎凋病、根腐萎凋病、半身萎凋病の対処法

萎凋病と根腐萎凋病
この病原菌は発病して枯死した植物体内で、土壌中で生存し続ける厚膜胞子を形成します。そのため発病を繰り返すと、土壌中に病原菌が蓄積することになり、被害は大きくなってしまいます。
発病圃場には土壌消毒を行うのが効果的です。薬剤による土壌消毒の他、太陽熱消毒、蒸気や熱水による土壌消毒も効果的です。
発病の軽減には耐病性台木の利用もおすすめです。
半身萎凋病
萎凋病、根腐萎凋病同様、土壌伝染性の病害のため、薬剤や太陽熱による土壌消毒が効果的であり、耐病性台木の利用ももちろん有効です。
半身萎凋病には特徴的な対策もあります。やや乾燥した土壌、アルカリ性に近い土壌を好むこの病原菌は微小菌核を形成して土壌中に生存し続けますが、湛水状態が長期間続くと微小菌核が死滅します。そのことから、水田との輪作では被害が少ないことが知られています。そのため土壌中の病原菌を除去するのに、水田との輪作、夏場の湛水によるヒエ栽培が効果を発揮します。
他の野菜で抑制する方法も!?
本サイトでは、他の野菜との輪作で萎凋病を抑制する研究について紹介しています。
関連記事:野菜の萎凋病を抑制するのは野菜!?他の野菜を使った萎凋病対策を紹介
上記記事には、萎凋病を発病しやすい土壌環境なども紹介していますので、気になる方はぜひ合わせてご覧ください。
参考文献