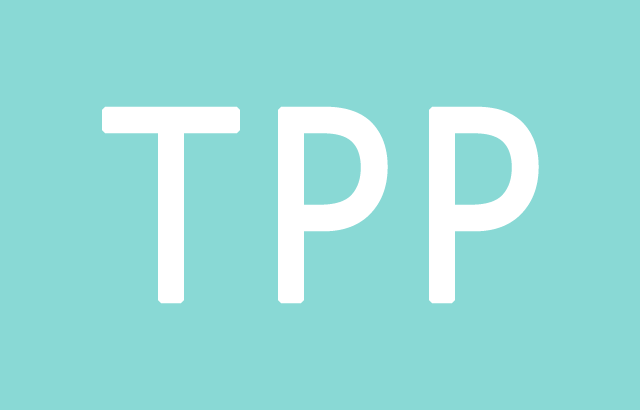カンキツ類の病害は多岐にわたりますが、時に異なる病害の症状が似ていることがあり、判別が難しいことも。そこで本記事では、カンキツ類の病害の中でも特に見分けにくい主要な病害についてご紹介していきます。
まぎらわしい病害の見分け方


まずは比較的見分けやすい病害からご紹介していきます。
そうか病とかいよう病
「そうか病」と「かいよう病」は病徴が似ていますが、それぞれに特徴的な症状と原因があります。
まず、そうか病はカンキツ類の葉や果実に現れる病害で、病原菌は糸状菌(Elsinoe fawcetti)、主にウンシュウミカンやレモンに発症します。病斑は葉にいぼ状の突起が生じる「いぼ型病斑」やかさぶた状の「そうか型病斑」、また両者が混ざった病斑ができます。果実にも同様の病斑が生じます。これらの病斑は商品価値を落とします。そうか病は雨や湿度が高い時期に多発します。
一方、かいよう病の病原菌は細菌(Xanthomonas citri subsp. citri)。かいよう病は、特にオレンジやグループフルーツに深刻な影響を与えます。レモンやナツダイダイでも発生し、ウンシュウミカンの場合は、夏の台風など悪条件が重なると発病することがあります。最もかいよう病の発病が少ないのはユズ、キンカンです。病斑は葉や果実の表面に茶色の潰瘍(かいよう)として現れ、周囲に黄色のハロー(輪状の変色)が見られるのが特徴です。この病気もカンキツ類の商品価値を大きく低下させます。かいよう病は、特に夏の台風や春先の多湿な気候によって発生しやすくなります。
そうか病とかいよう病の違い
これらの病気は、ウンシュウミカンなどの夏秋梢(夏から初秋に伸びた枝)に現れる初期症状が似ていることから区別が難しく感じられることがありますが、病斑の形状や周囲のふちどりの色などで見分けが可能です。前述した通り、そうか病の病斑はいぼ型か、平らでガサガサした表面が特徴的なかさぶた状のものが生じます。一方、かいよう病には「いぼ型」や「そうか型」といった区別はなく、病斑の周囲が水浸状となって、そのまわりに黄緑色のふちどりが見られるのが特徴です。
また発生するカンキツ類の種類に違いがあります。そうか病はウンシュウミカンやレモンに多く見られますが、オレンジ類やハッサクなどは耐病性品種です。一方、かいよう病はオレンジやグループフルーツ、レモンやナツダイダイに多く見られます。
黒点病とさび果


黒点病とさび果は、どちらも果実の外観を悪化させ、商品価値を低下させます。
まず、黒点病は糸状菌(Diaporthe citri)によって引き起こされる病気で、ウンシュウミカンやオレンジ類を含む広範なカンキツ類に発生します。葉や果実の表面に黒点ができますが、この黒点は病原菌に対するカンキツ類の防御反応によるものであり、黒点中には病原菌はほとんど存在していません。樹上の枯れ枝や圃場内に放置されている枯れ枝に形成される分生子(菌糸の一部が伸びて先がくびれてできる胞子)が伝染源となり、これらの分生子が雨滴によって飛散して、果実に感染します。黒点病は高温多湿な環境で多発し、特に長時間の雨や湿気が続いた後に発病します。
次にさび果です。さび果は炭疽病という病害によって発生し、その病原菌は糸状菌(Glomerella属またはColletotrichum属)です。これらの菌が果実や葉に感染することで褐色の病斑ができます。さび果は主に果実にのみ発生します。病原菌は枯れ枝上に胞子堆(ほうしつい:胞子がたくさん形成されて積まれた状態)を作り、黒点病同様、降雨によって分生子が伝播します。
黒点病とさび果の違い
どちらも果実に黒点や斑点を形成する点で似ていますが、いくつかの違いがあります。
| 特徴 | 黒点病 | さび果 |
| 斑点 | 小さく黒色 | 黒点病の斑点よりもさらに小さく、色も褐色〜紫褐色 |
| 病斑の形状 | 流紋状の病斑が見られる | 流紋状の病斑は生じるものの、黒点病に比べるとその形は不鮮明ではっきりしない |
| 果実への発病 | 未成熟な果実や日陰の果実や葉に発生する | 1月以降、果実が成熟し始めてからでないと発症しない。発病は果実に限られる |
| 発病する種類 | 広範なカンキツ類に発生 | 夏ミカン、レモン、グレープフルーツなどで発病する。温州ミカンには発病しない |
| 貯蔵中 | 貯蔵中に進展しない | 貯蔵中に病斑が進展する |
黒点病と銅の薬害
前述では、黒点病とさび果を比較しましたが、次にご紹介するのは黒点病と銅の薬害です。
銅の薬害は、カンキツ類に使用される銅剤(ボルドー液など)が過剰に散布されることで発生するもので、黒点病と似た黒点を形成します。特に、軽度の薬害と黒点病の病徴はきわめて類似しており、見分けにくいとされています。
黒点病と銅の薬害の違い
軽度の薬害と黒点病の病徴はきわめて類似していますが、一般的には銅剤による薬害で生じる黒点は一般的に大きく、不整型で表面がザラザラしているのが特徴です。銅剤の薬害がきわめて激しい場合には星型を呈するため、見分けやすくなります。
また発生が多い部位に違いがあります。黒点病の場合、特徴的な黒点は日陰部分に多く見られます。一方銅剤の薬害は、日なたの部分に発生が多く見られます。
ただし、やはり症状だけから判断するのは難しい場合も多いため、両者を見分ける際は銅剤の使用有無やその種類、濃度、使用時期などを総合的に判断することが重要です。
参考文献:夏秋啓子編『植物病理学の基礎(農学基礎シリーズ)』(農文協、2020年)
参照サイト:植物防疫基礎講座 病害の見分け方 9