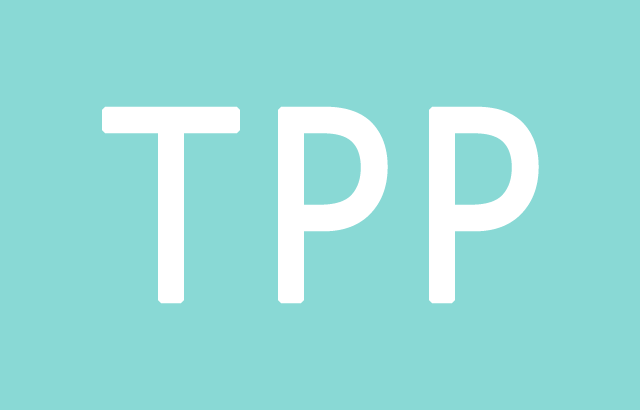根こぶ病は作物の根に大小の「こぶ」ができる土壌伝染性の病気です。根こぶ病は特徴的な「こぶ」のほか、アブラナ科の植物にしか感染しないなどの特徴があります。一度発生すると、防除が難しい厄介な病害の1つです。
被害の特徴

根こぶ病の特徴はなんといっても根に生じる「こぶ」です。ただし、こぶは地下にある根に形成されることから、作物の外見上はほとんど変化が見られず、そのことが早期発見の難しさにつながっています。
根こぶ病に感染した株はどうなるか
根こぶが次第に肥大していくにつれて、地上部へ水を送り込む導管が圧迫されていきます。すると、葉は萎れるようになります。根こぶ病に感染した株は、とくに晴天が続いたあとなどに異常な萎れが見られるようになります。
根こぶの様子
根にこぶが生じる症状が表れるのは根こぶ病に限りません。ネコブセンチュウという害虫もまた根にこぶを生じさせます。ただし、ネコブセンチュウがあらゆる種類の植物に帰省するのに対し、根こぶ病はアブラナ科の植物にしか発生しません。
また、こぶの形状にも違いがあります。根こぶ病の場合、つぶの形はごろっとした見た目となります。一方、ネコブセンチュウの場合、こぶそのものは小さく、根のところどころが膨れるか、ジュズ状につながっているかのいずれかとなります。
根こぶ病が厄介な理由
根こぶ病の原因菌は糸状菌(かび)の一種です(学名は「プラスモディオフォラ・ブラシカエ」(Plasmodiophora brassicae)、以下ネコブカビ)。
厳しい環境を生き延びるから厄介!
土壌中のネコブカビは「休眠胞子」と呼ばれる状態でアブラナ科の根が伸びてくるのを待ちます。休眠胞子とは発芽前の状態を指し、運動性はありませんが、頑丈なキチン質の細胞壁で構成されており、温度変化や水に耐え抜きます。
おそろしいのが、この休眠胞子の状態であれば、土壌中で7年〜10年以上生存できることです。発芽に適する条件がそろうまで、ひたすらアブラナ科の根が伸びてくるのを待ち続けるところが、一度発生すると防除が困難な理由の1つといえます。
根こぶ病の対策

発病の危険性を調べる
土壌中には実に多様な微生物が存在しています。アブラナ科野菜を栽培していない土壌であっても、ネコブカビの休眠胞子は存在するといえます。とはいえ、休眠胞子の密度が土壌1gあたり1000個以上程度の場合は発病しません。1gあたりの密度が1万個以上になると発病し始めます。
発病の危険性は簡易的に診断することができます。
<使用するもの>
- 3寸程度(約9cm)の植木鉢5つ
- 少量の砂や鉢底石
- コマツナの種子(または対象圃場で作付予定の作物の種子)
- 使用済みの食品トレー(植木鉢の下に設置して深さ1cmほど水を張れる容器)
<診断方法>
- 植木鉢の底に少量の砂や鉢底石を入れておく
- 畑の中央を起点に、サイコロの5の目に位置する場所から同量ずつ土をとる
- 2.の土をよく混ぜたうえで、1.の植木鉢に詰める
- 3.にコマツナの種子を20粒ほどまく
- 4.を食品トレーに載せて、深さ1cmほどに水を張る
- 1ヶ月ほど栽培し、根を抜き取り、こぶの有無を確認する
6.で根こぶが見られた場合には、土壌中の休眠胞子密度が高まっていると考えることができるので、迅速に防除対策を行います。
ネコブカビが苦手な環境にする
まず、ネコブカビが好む環境についてご紹介します。ネコブカビは他の糸状菌(かび)同様、湿気を好みます。また、酸性が強い土壌も好みます。日本は雨が多く、土壌の酸性化が進みやすいため、ネコブカビにとって非常に生育しやすい環境といえます。
ネコブカビは排水性が悪く、酸性の強い土壌を好むわけですから、根こぶ病対策はその条件に当てはまらない土づくりが重要です。
酸性土壌の場合には、土壌pHを7.2以上に上げることで発生を抑えられます。後藤逸男・村上圭一『おもしろ生態とかしこい防ぎ方 根こぶ病 土壌病害から見直す土づくり』(農山漁村文化協会、2012年)では、根こぶ病対策のために思い切って土壌pHを7.5まであげることが推奨されています。
土壌pHを高める際注意したいのが、ホウ素やマンガンといった微量要素欠乏の発生です。大量に施用する必要がありますが、転炉さいであれば、微量要素の欠乏を気にせず、土壌pHを高めることができます。
発病しにくい作物を活用する
根こぶ病はアブラナ科の作物に特有の病害ですが、同じアブラナ科作物によっても発病のしやすさに違いがあります。ハクサイやカブ、ノザワナなどは根こぶ病が発生しやすいですが、キャベツやカリフラワー、ブロッコリーは先述した野菜に比べると、根こぶ病に強いです。
そして、辛味成分をもつ葉ダイコンやダイコンは発病しません。
そこで活用されるのが、発病しないアブラナ科野菜をおとりに、作物を根こぶ病から防除するという方法です。
葉ダイコンやダイコンであっても、ネコブカビの休眠胞子はそれらの根が近づくと発芽し、感染します。しかし根こぶの形成には至りません。
ネコブカビの生活環は以下の通りです。
- 土壌中の休眠胞子から遊走子(運動性のある胞子、第一次遊走子)が放出され、根毛に寄生する
- 根毛に寄生した遊走子は根の中で休眠胞子を形成する
- 第二次遊走子となった2.は一度根毛の外に放出され、主根あるいは側根に感染する
葉ダイコンやダイコンなどのおとり作物は、1.にあたる第一次感染まではするものの、発病しないため、このような作物にネコブカビを感染させることで、土壌中の休眠胞子を一掃する方法があります。
代表的なおとり作物には、「おとり大根 CR-1」や「ヘイオーツ」(エンバク)などがあげられます。
雑草の管理、罹病株の処理方法に注意
ナズナやタネツケバナといった雑草もまた根こぶ病を発病します。ほ場周辺に生えている雑草が根こぶ病の感染源となる可能性があるため、雑草管理も根こぶ病対策に有効です。
また、ほ場で作付している作物に異常な萎れが見られた時、根こぶ病かどうかを確認するために作物を抜き取るかと思いますが、この際も注意が必要です。
ネコブカビに感染した根を土壌中に残さないために、抜き取る際はスコップなどを用いて周りの土と一緒に掘り上げてください。また掘り上げた後、穴の周辺に根こぶが残っていないかも確認してください。
根こぶが見られた場合には、同じ症状が見られる株をすべて抜き取ってください。この際、罹病株を土壌中にすき込んだり堆肥に利用したりするのはNGです。畑の外に放り投げるのももちろんNG。ほ場から離れた場所やごみ焼却場などで焼却処分してください。
ネコブカビは雨や風の影響のほか、人によっても運ばれます。根こぶ病が発生した畑で使用した作業靴や農業機械などにはそのほ場の土が付着しているはずです。土の移動によって他のほ場に根こぶ病が広がるのを防ぐためには、ほ場から離れた場所で付着した土を水で洗い流したり、根こぶ病が発生した畑で使用した機材等はできる限り使い回さないようにしたりすることが大切です。
参考文献:後藤逸男・村上圭一『おもしろ生態とかしこい防ぎ方 根こぶ病 土壌病害から見直す土づくり』(農山漁村文化協会、2012年)
参照サイト
- アブラナ科野菜の恐ろしい病害、それが「根こぶ病」
- 病害名:根こぶ病 – キャベツ
- 根こぶ病
- アブラナ科野菜根こぶ病に対するおとり作物としてのエンバク(ヘイオーツ)の利用
- STOP根こぶ病!効率的な防除を!-レベル別の対策によるコスト・労力の削減
- ネコブセンチュウ対策/奈良県公式ホームページ
- ネコブカビ類伝搬性ウイルスとその媒介生物の生物学的及び遺伝的多様性
- アブラナ科野菜根こぶ病の 診断・対策支援マニュアル
(2024年5月10日閲覧)