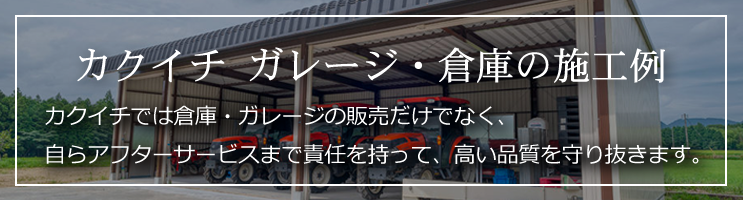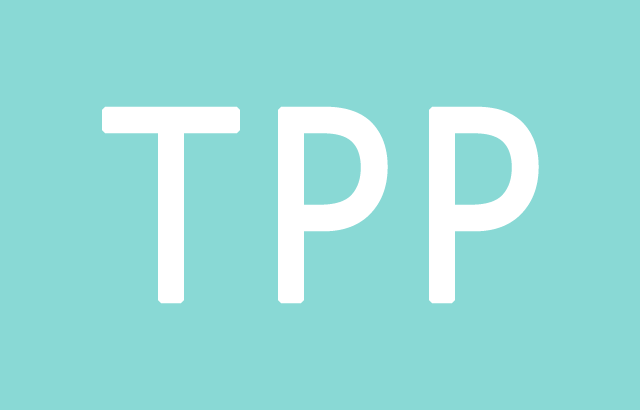いもち病とは、日本の水稲栽培において最も深刻な被害をもたらす病害の一つです。
病原体はPyricularia oryzae(Magnaporthe oryzae)というカビの一種で、この菌がイネのさまざまな部位に感染し、大きな損害を引き起こします。いもち病は、葉や茎、穂に病斑を作り、感染した部位は最終的に枯死することが多いです。
いもち病の特徴


いもち病は、病原体が感染する部位によってさまざまな名称で呼ばれます。
苗いもちの特徴
たとえば、いもち病は種子伝染性の病気なのですが、罹病種子に由来して最初に発生するものは「苗いもち」と呼ばれます。苗いもちは、育苗期間中の苗の鞘葉や不完全葉などに灰緑色の病斑を生じます。
苗いもちの病斑上では多数の分生子がつくられます。これらが飛散し、育苗期間中の葉に感染すると、次に紹介する「葉いもち」が発生します。
葉いもちの特徴
本殿に移植された罹病苗などから分生子が飛散すると、葉に紡錘状の葉いもち病斑が発生します。その後、いもち病の発生に適した気象条件が続くと、病斑上の分生子の飛散と感染が繰り返されることになります。その結果、株全体が萎縮し(「ズリコミ症状」と呼ばれる)、出穂することなく枯死してしまいます。
穂いもちの特徴
出穂後に発生したもの、穂首や枝梗に感染したものは「穂いもち」と呼ばれます。穂の感染部位が枯死すると、養水分が穂や籾に供給されなくなります。そのため、不稔となり、収量に大きな影響を与えることになります。
病斑の進行について
感染初期は、葉に灰緑色で水浸状の楕円形病斑が現れます。病気が進行するにつれて褐色に変わり、中央部分が灰褐色の紡錘形に壊死した典型的な病斑ができます。この病斑は葉や穂に発生し、感染が広がると株全体の萎縮、枯死につながります。
ちなみに、病斑の状態によって、感染しやすい、病気が多発しやすい状態か否かを見分けることができます。もし、病斑の中央部が崩れて灰色〜灰褐色をしており、そのまわりが紡錘形に褐色になっている場合は、胞子の形成量は多くありません。ただし、中央部が小さく円形で、健全部との境目が黄色い場合には、病気が進行している病斑といえ、胞子の形成量が多く、周囲へ伝染しやすいものといえます。
なお、病斑の画像を見るには以下のサイトがおすすめです。
発生要因について


まず、いもち病の発生に最も影響を与えるのは気象条件です。気温が15〜25℃程度といった比較的冷涼な気候、湿度が高く、長期間の弱い雨が続く状況下では、いもち病菌の分生子が多く形成されるため、発病が助長されます。長雨や冷害が続く年にはいもち病が多発する傾向にあります。さらに、強風でイネが傷つくと、そこからいもち病菌が侵入しやすくなり、感染が広がる原因にもなります。
また、いもち病の病原体は稲わらや土壌中で越冬することができ、それらが翌年の第一次伝染源となります。そのため防除を行う際には、被害を受けた作物残渣やわら、籾殻の適切な処分も重要になってきます。
そのほか、泥炭土壌や腐植過多土壌、老朽化土壌で発生しやすいと言われています。これらの土壌では、夏場に急激な温度上昇が起こりやすく、イネの抵抗力が低下します。また、砂土では肥料の吸収が過剰に行われることがあり、これも発病を助長する一因となります。
加えて、窒素の過剰使用は特にいもち病の発生に関与しています。窒素肥料が多いと、イネの組織が軟弱になり、病害に対する抵抗力が低下します。また、リン酸やカリの過剰施用も発病を助長することがあるとされています。
一方で、ケイ酸の適切な施用は、イネの葉表皮にケイ酸層を形成し、いもち病菌の侵入を物理的に阻止する役割を果たします。
予防策・対策について


種子消毒
いもち病の主な伝染源は罹病した種子や稲わら、籾殻です。そのため、健全な種もみを確保するために、必ず種子消毒を徹底してください。健全な種子を種子消毒をした後に播種するなど、伝染源を断つことがいもち病対策においては非常に重要です。
加えて、播種後、籾が露出してしまうほど覆土が浅いと発病しやすくなるため、厚播きせず十分な覆土を行うことも発病リスクの低減につながります。
窒素肥料の適正使用
窒素肥料の過剰使用は、いもち病の発生リスクを高めます。そのため、適正量を守ることが大切です。いもち病の発生が確認された圃場では、追肥を控え、防除を優先してください。
病害に強い品種の導入
いもち病に対する抵抗性遺伝子を持つ品種が数多く開発されています。これらの品種を利用することで、いもち病の発生リスクを軽減することが可能です。ただし、いもち病菌も進化を続けています。そのため、複数の抵抗性遺伝子を持つ品種を選ぶことが望ましいです。
薬剤散布
いもち病が発生した場合には、早めに薬剤を散布することが重要です。
まず本田での発生を防ぐために、葉いもちの初期発生を予防する育苗箱施用剤や水面施用剤の利用が有効です。
葉いもちが発生した際は、発見から1週間以内に散布を行います。常発地などでは、粒剤をできるだけ初発前に散布しておくのがポイントです。
加えて、穂いもちに進行する前に対策を講じるのが鉄則。葉いもちが多発し、上位葉に病斑が見られる場合には、穂ばらみ末期と穂揃期の2回散布を行うことが推奨されます。上位葉に病斑が見られない場合には、穂揃期に1回薬剤散布を行います。
ただ、出穂の時期に降雨が続く場合は、いもち病の感染が広がる気象条件であることから、葉いもちの多い少ないに関わらず防除を行ってください。
なお、農薬を散布する際は、農薬ラベルに記載されている使用上の注意をよく確認してから使用してください。そして同じ系統の薬剤を連用することは耐性菌を生じさせる恐れがあります。異なる系統の薬剤を交互に使用してください。
参考文献
- 夏秋啓子『植物病理学の基礎』(農山漁村文化協会、2021年)
- 米山慎吾他『仕組みを知って上手に防除 新版 病気・害虫の出方と農薬選び』(農山漁村文化協会、2022年)
参照サイト