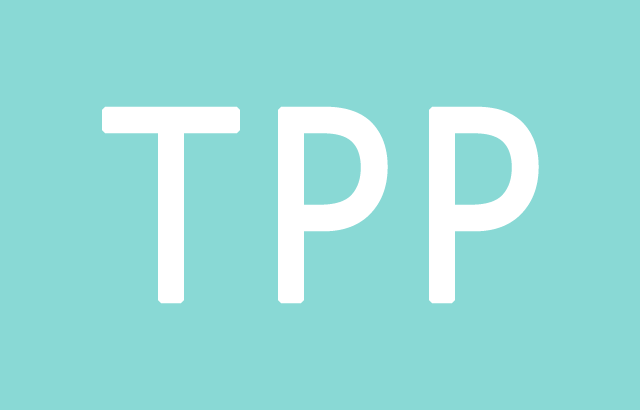主食用米の需要量は年々減少しています。人口減少や食の多様化などが要因となり、2015年から2022年にかけては年平均約11万トンの減少が見られました。
なお、2023年産の主食用米の需要(2023年7月の日本経済新聞にて発表された速報値)は681万トンで、前年より1.4%減少し、2年連続で過去最低を更新しています。
また、米の需給状況の指標の1つで、米価と関係のある米の民間在庫量は増加傾向にあります。特に、新型コロナウイルス感染症による中食・外食需要の減少によって、2023年6月末には民間在庫量が適正水準である200万トンを大幅に上回る結果となりました。米価を安定させるためには作付面積のさらなる減少が必要とされています。
新型コロナウイルスの影響が落ち着き、経済活動が正常化し始めたことで、主食用米の外食向け需要が戻ると見込まれていますが、人口減少などで国内市場の縮小は続いています。農林水産省は農家に対し、需要に見合った生産を呼びかけるなどしています。
そんな折、注目を集めるのが米の主食用米「以外」の需要です。
米の新たな可能性


米粉の活用


これまで米粉の価格は製粉コストを含めて比較的高価とされてきました。しかし、近年は輸入小麦の高騰や、前述した主食用米の需要減少に伴い、小麦に代わる加工用原料として米粉が注目されています。
米粉の利用拡大には、政府の取り組みが大きな影響を与えています。農林水産省は、米粉と米の消費拡大を目指したプロジェクトを展開し、TVCMやインターネットを活用したレシピ提案、外食産業やスーパーマーケットとの連携を進めています。
米粉はパンやケーキ、麺類など新しい用途が開発されるだけでなく、米粉の活用方法も多様化しています。たとえば、米殻を加熱処理して裏ごしピューレ状に加工した米ピューレや、アルファ化米粉などの登場により、米粉は製パンや粘度調整、油脂の代替など、幅広い用途に対応できるようになっています。
米粉用米の生産も増加しており、専用品種「ミズホチカラ」や「笑みたわわ」など、加工適性や収量に優れた品種が開発されています。2023年度の米粉用米の生産量は前年度より10%減少しましたが、需要量は18%増加しています。農林水産省は、24年度には米粉の需要量がさらに21%増の6万4,000トンになると見込んでいます。
グルテンフリー志向の高まりも米粉の需要を後押ししています。米粉の市場はまだ小さいものの、健康志向や小麦グルテンを避けるニーズに応える商品が増えており、今後の普及が期待されます。米粉に関する規制や制度も整備されており、特に平成30年から運用されている「ノングルテン米粉第三者認証制度」では、米粉製品のグルテン含有量が1ppm以下と確認された製品は「ノングルテン」の表示ができるようになり、製品のアピールにつながっています。
米粉は、健康や代替食品として今後も需要拡大が期待される分野といえ、今後の米の消費拡大に向けた重要な戦略となるのではないでしょうか。
飼料用米の拡大
家畜の餌として利用される飼料用米は、輸入トウモロコシの代替品として注目されており、近年、その作付面積が急増しています。2004年には全国で44ヘクタールだったものが、2016年には9.1万ヘクタールに達しました。
なお、2024年産の飼料用米の作付面積は、全国で9.9万ヘクタールと推定されています。これは、2023年産に比べて3.5万ヘクタール減少していますが、基本計画における2030年目標の9.7万ヘクタールを上回っています。
栃木県や茨城県、青森県など関東や東北地方を中心に作付面積が拡大しており、これらは国内の飼料用米の自給率向上に寄与しています。
また飼料用米の品種改良も進んでおり、「モミロマン」や「べこごのみ」、「きたあおば」といった強健で高収量の品種が開発されています。これらは省力・低コスト栽培への貢献が期待されています。
一方で、課題もあります。飼料用米の供給には、家畜用飼料の主原料であるトウモロコシと同等またはそれ以下の価格での供給が求められます。また、安定的な供給体制の確立や、集荷・流通・保管施設の設備も必要とされており、さらなる拡大に向けてはこれらの課題を克服する必要があります。
バイオエタノールへの活用
米をエネルギー源として活用する取り組みが進んでいます。
米を原料としたバイオエタノールの製造は、水田機能を維持しつつ、余剰米をエタノールに変換して、エネルギー資源の確保を目指すだけでなく、緊急時には食用として活用することもでき、食料安全保障にも貢献できるというメリットから注目されています。
バイオエタノールへの活用は以前から行われていました。たとえば新潟県では2005年からJA全農と共同でバイオエタノール製造に取り組んでおり、2007年には農林水産省のモデル事業に採択され、米の生産から副産物の活用まで一貫したプロジェクトが実施されました。この計画では、バイオ原料となる品種を使用して、エタノールを製造し、そのエタノールをガソリンの3%混合して、県内のJAスタンドで販売するというものでした。冷夏など気象条件の影響で原料米の収量が目標値を下回り、エタノールの製造量も当初の目標に届かないといった事態にも見舞われましたが、このプロジェクトではバイオエタノールの販売量が当初の目標を超えたり、副産物として籾殻を燃料や飼料、土壌改良剤として活用する道が開ける結果となりました。
日本国内では、過去に米からエタノールを製造する実験が行われていたものの、高い生産コストが障壁となっていました。しかし近年はゲノム編集技術によって超多収性の米が開発されており、再び米をエネルギー源として活用する可能性が高まっています。また、エタノール燃料は、温室効果ガスの排出を抑えることができ、カーボンニュートラルの実現に貢献するため、環境対策としての意義も増しています。
さらに、米をエネルギー資源として活用することには、日本の耕作放棄地の活用や温暖化対策の観点からも大きな可能性があります。アメリカ穀物協会の試算によると、日本の約42万ヘクタールの耕作放棄地で多収米を栽培すれば、年間190万キロリットルのバイオエタノールを生産でき、これは日本のガソリン消費の約4%に相当します。
これを実現するためには、米作の転換や技術の向上などが必要になります。また、バイオ原料米の価格が低いことから、農家への支援は必要不可欠です。バイオエタノールの原料となる米の生産に対する安定的な支援体制、そして農業とエネルギー分野の連携を深める政策が求められます。
とはいえ、今後、バイオエタノールの生産は原油高騰や環境問題への対応策として再検討され、米の新たな利用方法として注目されるのではないでしょうか。持続可能な農業のあり方とエネルギー供給の実現に向けた重要な一歩となるかもしれません。
参考文献:八木宏典『図解知識ゼロからの現代農業入門』(家の光協会、2019年)
参照サイト