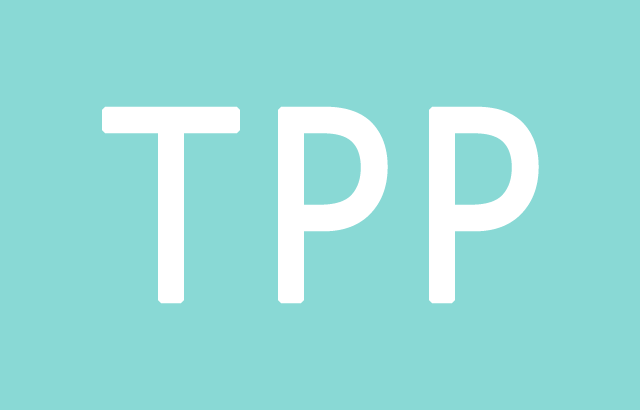近年、農業分野では環境への配慮や生産性向上を目指した技術革新が注目を集めています。そこで本記事では、栽培管理をより合理的に行うことができる、前作を活かした栽培技術事例を紹介していきます。
ブロッコリーとカラシナの前作でナス半身萎凋病の発病を抑制


病害虫の管理において、連作よりも輪作が有効であることが広く認識されています。特に、異なる科の作物を組み合わせて数年間隔で栽培を行うことは、病害虫の予防に効果的です。たとえば、ジャガイモの前作としてイネ科作物を作付けすると、ジャガイモのそうか病の発病を軽減する効果が高いことが報告されています。
本記事では、ブロッコリーを前作として栽培することにより、ナス半身萎凋病の発病が抑制されることについてご紹介していきます。
アメリカ・カリフォルニア州で行われた研究では、ブロッコリーとの輪作がカリフラワー半身萎凋病の発病を抑制することが確認されていました。群馬県で行われた実験では、ブロッコリーを前作、ナスを後作として栽培した場合、ナス半身萎凋病の病原菌の減少が確認され、発病株の割合が無処理区と比較して低下しました。
さらに、カラシナを前作として栽培し、その後、土壌にすき込むことでもナス半身萎凋病の発病抑制効果が確認されています。カラシナに含まれるアリルイソチオシアネート(天然の辛味成分で、高い抗菌・防カビ性を持つ)には、ホウレンソウ萎凋病菌を抑制する効果が知られています。実験では、カラシナをすき込んだ区でナスの発病株率が低く抑えられる結果となりました。
大麦の前作で雑草を抑え、大豆の増収へ


東北農業研究センターの研究によると、不耕起で栽培する大豆の前作として大麦を栽培することで、雑草抑制の効果が得られ、大豆の収量を20%程度増加させることが実証されました。
東北地方では、気象条件から畑作物が単作となり、年間を通じて農地があいていることが多く、収穫を目的としないカバークロップを導入することが期待されています。カバークロップは雑草防除を目的に使用される作物で、代表的なものにはライグラス類やライ麦、大麦などがあります。これらの作物は、栽培期間が短くても土壌浸食防止や雑草抑制の効果を発揮します。
大豆の増収につなげるためには、前作に大麦を栽培し、大豆播種時に未熟な子実を含む大麦の地上部を細断して地表面に敷きます。これにより、カバークロップが地表面を覆うことになり、雑草の発芽を抑制します。また、狭畦栽培(大豆の畦幅を狭めて雑草の発生を抑え、除草作業を省力化する栽培技術)と組み合わせることで、中耕などの中間管理作業を省略できるうえ、雑草の量を減らすことにもつながり、大豆の収量を最大20%程度高めることができます。この効果は、播種時に除草剤を散布することでさらに高まると報告されています。
もちろん、除草剤を散布しなければ、大豆栽培における除草剤使用を減らせる可能性がありますし、雑草抑制の効果だけでなく、土壌に有機物を投入することで地力の維持にも貢献する技術といえます。
有機農業や環境負荷低減を意識した栽培方法として、さまざまな農地で活用されることが期待されています。
ナスの枝を支柱に活用


最後にご紹介するのは、前作のナスの枝をそのまま次作の支柱にするという方法です。
2024年4月6日に公開された日本農業新聞の記事によると、この方法はキヌサヤエンドウとナスの両方を栽培している農家が採用している手法です。支柱やネットを設置する手間を省くことができ、生産コストの抑制に貢献しています。
通常、キヌサヤエンドウの栽培には支柱やネットを設置する必要がありますが、前作のナスの枝を採用することでこの手間が省略できるといいます。具体的には、収穫を終え、枯れたナスの株元にキヌサヤエンドウの種をまき、伸びてきたつるをナスの枝に誘引します。なお、ナスの枝を支柱にするだけでなく、ナス栽培で使用した畝やマルチも再利用できます。
前作を活用する技術は、農業における資源の循環利用を促進します。より合理的な栽培管理、環境負荷低減等につながるのではないでしょうか。持続可能な生産方法の一つとして今後も注目を集めることが予想されます。
参照サイト