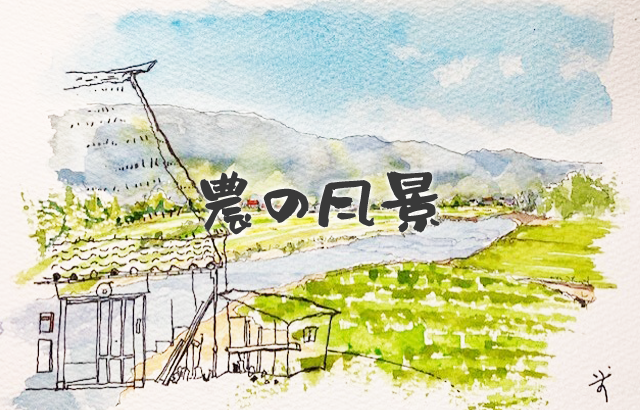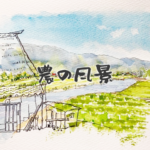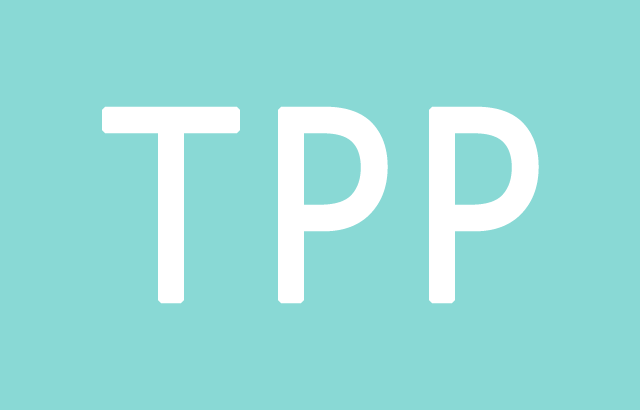今回は、日本の農家は、なぜ、法人化と大規模化を選択しなかったのかを「規模の経済」をキーワードにして学問的視点から考えてみます。
農業経済学と言う学問があります。農業経済学は、農業が抱えている様々な経済的な問題を経済学、経営学、社会学といった社会科学から研究する学問です。この農業経済学の研究では、国が主張している稲作農業の大規模化についてどのように評価しているのでしょうか、まず、この問題について、農業経済学ではどのように考えていたのかを見ておきましょう。
規模の経済性を検証する一つの方法として生産関数によるアプローチがあります。生産関数とは、生産要素(土地、労働、資本など)の投入量と、それによって得られる最大産出量との関係を関数式で表したものです。
生産量をY、土地をT、資本をK、労働をⅬとすれば、生産関数はY1=F(T、K、L)で表されます。
この生産関数を使い「規模の経済」を説明すれば次のようになります。
稲作生産に必要な土地、労働力、資本などの生産要素を2倍にすれば、生産関数は、Y2=F(2T、2K、2L)となります。
この時、左辺の生産量Y2が、Y2 > 2Y1 ならば、規模の経済が存在していることになります。
つまり、土地、労働、資本の生産要素を2倍にしたら、生産量は2倍以上になり、収穫逓増、規模の経済が発生したことになります。
なお、Y2 < 2Y1 ならば、収穫逓減、つまり、土地、労働、資本の生産要素を2倍にしたら、生産量は2倍未満になり、規模の経済が発生しないことになります。
また、Y2 = 2Y1 ならば、収穫不変、つまり、土地、労働、資本の生産要素を2倍にしたら、生産量も同じ2倍になり、規模に関係なく収穫量はかわらないことになります。
この生産関数を特定化し、稲作経営で計測し規模の経済が存在するのかを検証した研究は数多くあります。これらの研究を総括すると、稲作農業においては小規模層においては規模の経済は存在するが、大規模層では規模の経済は存在しないことが農業経済学会ではコンセンサスを得ていると考えられています。
さらに、稲作の費用関数の計測から日本の稲作生産の費用曲線はⅬ字型、つまり、規模が大きくなっても、ある規模以上ではコストが下がらないことが明らかになりました。
これらの研究から、我が国の大規模稲作農業経営では規模の経済が発生しないから、依然として小規模稲作経営が存在している理由の一つとなっています。
規模の経済が存在する小規模層がその上の階層に移動する動きは、1950年から1960年にかけての中農肥大化傾向として認められましたが、それ以降は両極分化傾向が認められ、日本の稲作農業は、依然として小規模・零細稲作経営が中心なのです。
この事実から、規模の経済以外にも小規模零細農家が存続する理由があるのではないかとの疑問が学会内でおこり、多くの研究者はその理由を考え、自家労働評価の問題、労働市場の特殊性、農地市場の性格、生産調整政策などがあることを突き止めました。
自家労働評価の問題とは、例えば、田植えをする時に、自分の労働力をいくらに見積もるかと言うことです。極端な見方をすれば、小規模農家が自分の自給労働をゼロ円と評価していれば、当然、小規模農家の生産費は安くなります。
国や農業評論家たちは、米価が下がれば大規模農家は小規模農家よりコストが安いから小規模農家は稲作生産から撤退し農地が大規模農家に集まり規模拡大が進むと考えていました。ところが、現実には小規模農家は自分の労働力を安く評価しているのでコスト割れせずに稲作生産を継続しているのです。
この規模階層別の自家労働賃金を均衡価格という概念で推定した研究が多くあります。この均衡賃金とは、農家が利潤極大化行動、あるいは費用最小化行動をとったと仮定した場合に、均衡賃金は理論的に導けるので、生産関数や利潤関数や費用関数を推定し求めることが出来るのです。その結果、小規模階層ほど均衡賃金は安く、また、時代とともに、均衡賃金の階層差は拡大したことが示されました。
労働市場の特殊性とは日本における兼業農家の存在に関わるものです。
農村における労働市場は、新古典派経済学の仮定する労働市場の均衡水準を満たしておらず、就労条件の不安定や低賃金など労働市場が2重・3重に存在しています。特に、農村地域の労働市場は都市と比較して労賃水準が低い傾向にあります。
その結果、農村では労働賃金だけでは農家の生活を充足できないので、家計を補充するための農業所得が必要であり、小規模農業を続けざるを得ないということになります。その農村的労働市場の特殊性が、小規模農家を兼業農家として残していると言う考えです。
農地市場の性格では、農地は農地法によって農地として所有される仕組みです。
この農地法の存在が自作農主義を前提とした所有権移転による規模拡大が阻害されているとする見解です。また、2種兼業農家(兼業所得の方が農業所得よりも大きい農家)の多くが、土地資産保全のために農地を手放さず農業にとどまるために、農業生産性の向上に意欲をもっている優秀な農家に農地が集まらず、これが、日本農業衰退の原因となっていると主張した研究もあります。
一方、米価政策や生産調整は規模拡大の阻害要因であるとの考えがあります。これは、1942年から始まった米や麦などの価格や供給等を国が管理する食糧管理制度や、1971年から本格的に開始された生産調整(米の作付面積を制限し生産量を調整する政策)は、農地賃貸借や規模拡大の阻害要因だとする考え方です。この問題について、費用関数の計測を通し、作付制限の緩和、米価の引き下げは、兼業農家の農地保有性向を低め、規模拡大に寄与すると言う研究があります。
この研究によれば、生産調整を廃止し米価が下落すれば、規模拡大と構造改革は進むとなっています。これに対し全く逆の見解もあります。すなわち、米価の引き下げは、前述した自家労働力を安く評価している小規模層よりも大規模層に与える影響が大きく構造改革は進まないとの研究です。
次回からは、米価下落と規模拡大の関係について考察し、国は、「なぜ、企業的大規模経営の育成を政策目標にしたのか?」を考えてみます。
稲田宗一郎(いなだ そういちろう)