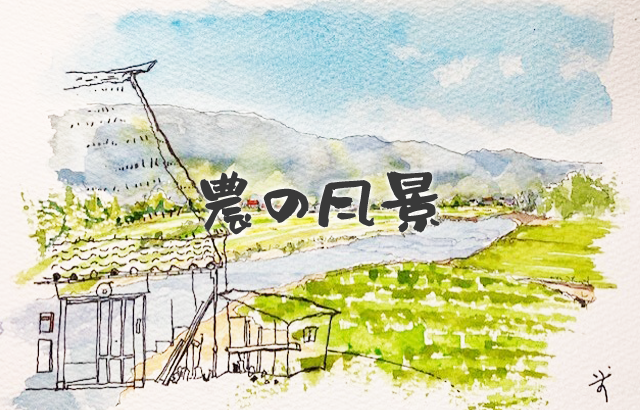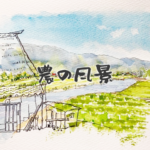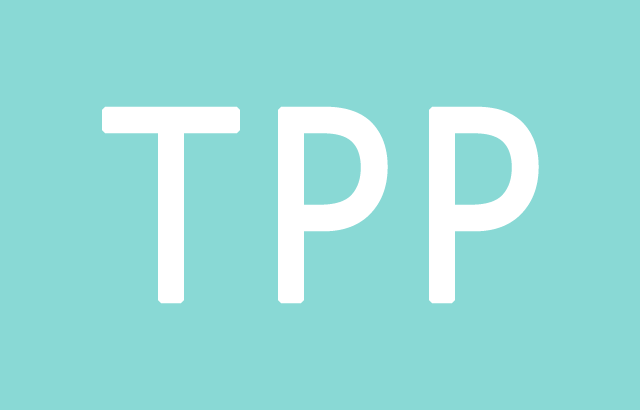前回、日本経済そのものが停滞している中で、政治家・官僚を含め国民の多くは「過去の栄光を再び」と言うドンキ・ホーテ的な「見果てぬ夢」を諦めきれないと述べました。
その典型的な考え方が、財務省における農業の考え方です。
.png)
.png)
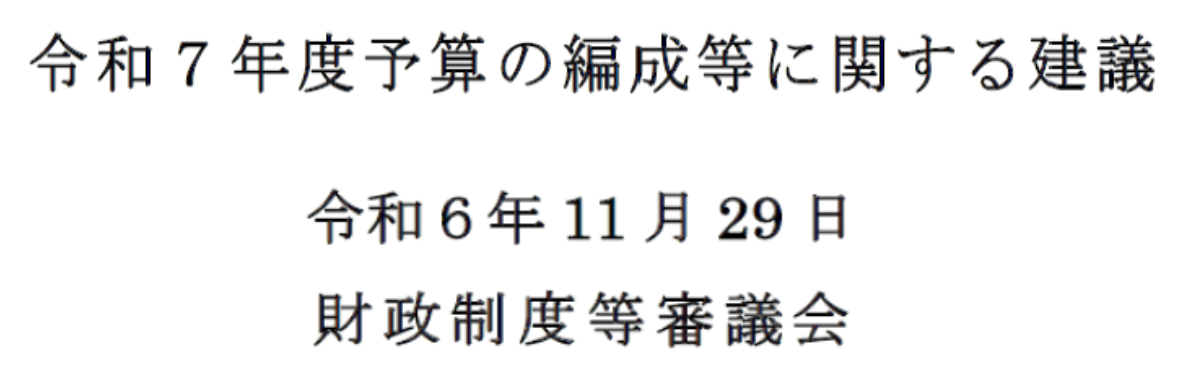
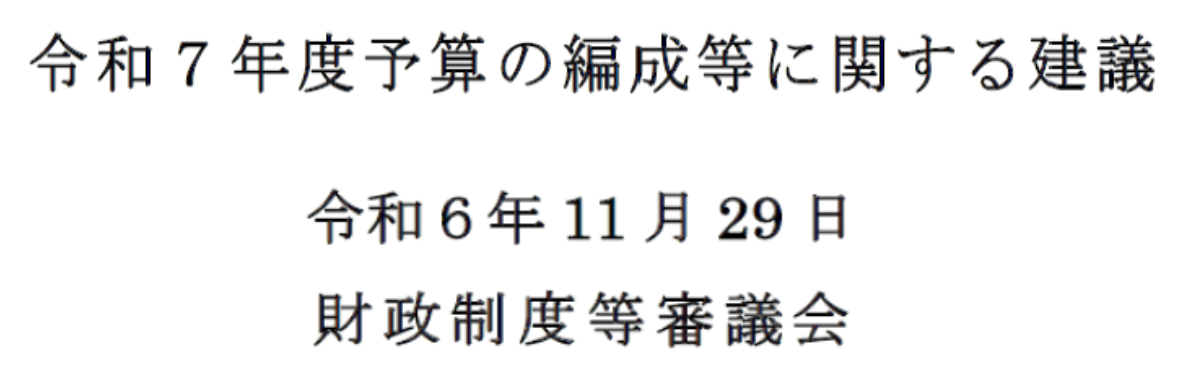
2024年11月末にまとめた「財政制度等審議会」がまとめた答申では、農業従事者の急減といった状況変化に対し、農業経営の⼤規模化や輸出の推進等により、多額の国⺠負担を伴う⽇本の農業を⾃⽴した産業へと「構造転換」するとしています。その削減のポイントは「足腰の強い水田農業への転換」であり、これは農林水産省の「食料・農業・農村基本法」の柱の1つである生産性の高い大規模農業の確立と共通しています。しかし、その政策的な意味合いは大きく異なっています。
財務省の資料はこちら
令和7年度予算の編成等に関する建議
その違いは食料安全保障の強化に関するものです。財務省は食料安全保障の確保を目標とした食料自給率を高めること自体が難しいという立場をとっています。
すなわち、「麦・大豆を含む土地利用作物には現状でも多額の財政支出を行っていますが、仮に小麦・大豆を国内生産することで食料自給率を1%引き上げようとすれば、畑地で400~500 億円程度、水田で800~900 億円程度の国費が必要となり、単純に食料自給率の向上を目指して国内生産の底上げを進めようとすれば、そのために必要な国民負担は相当な大きさになります。こうしたことを踏まえると、食料安全保障の確保においては、常に輸入と備蓄の活用という視点を欠いてはならない」と提案しています。
つまり、財務省は、国内農業を維持するための農業補助金は多額の財政負担が発生するので、この財政負担を減らすために輸入と備蓄を活用するとしているのです。
結論的に言えば、財務省は「日本には耕種農業、つまり、コストがかかるコメや麦や大豆はいらない。必要ならば輸入すればよいとの立場なのです。もし、コメの国内生産が必要ならば、大規模化してスマート農業を導入しコストダウンを実現し、外国のコメのニーズを研究し海外市場を開拓し輸出すること」を求めています。こうなれば、国民の税金を無駄な農業に支出しないですむと財務省は考えているのです。
さらに、現在実施している水田活用の直接支払交付金の飼料用米の助成政策を交付対象から外すとしています。この飼料用米の助成とは、水田を活用して飼料用米を栽培した場合には、水田活用の「戦略作物助成」として交付金を受け取れる仕組みです。この財務省の考えに反対できなかった農水省は、2023年度予算の10a当たり5.5~10.5万円の交付金金額を、2024年、2025年と下げて、2027年以降はこの制度自体を廃止するとしています。これに関連して「5年水張問題」があります。
国はコメの転作作物として大豆や麦、飼料作物を栽培する農家に対し水田活用の直接支払交付金を交付してきましたが、この交付金についても、「転換作物が固定化している水田の畑地化を促すとともに今後5年間(2022年~2026年)に、1度も水張りが行われない水田に対しては、2027年度以降、交付金は出さない」と政策を変更したのです。
この一連の農水省の政策変更は、新自由主義とグローバル経済のパラダイムを信じている「頭のよい、農業などは見たこともない」財務省官僚たちが考えたものです。
この新自由主義的な考え方を今回の「財政制度等審議会」の報告書から拾ってみると、以下に示すようにいたるところで見ることができます(下線は筆者)。
1)現在の農業の構造的課題は、生産・経営において多額の国民負担に基づく財政支援や種々の規制等が存在することにより、生産性向上・経営の効率化が十分に進まず、収益性の向上を通じた産業としての自立化が進まないことにある。(中略)こうした農業構造を今後も国民の多くの負担により支え続けることは持続可能ではなく、我が国の財政事情の厳しさを鑑みれば現実的でもない。何よりも、国全体としての喫緊の課題となった食料安全保障を強固なものとするため、農業構造を転換し産業としての自立を果たしていくことが強く求められている。(報告書:p116)
2)本質的に重要なのは、「農業の行く末は財政支援の多寡にかかっている」という発想から脱却し、法人経営や大規模化、輸出の推進等、可能な努力を積み重ね、多額の国民負担に支えられている日本の農業を自立した産業へと、まさに「構造転換」を果たしていくことであり、このことこそが、合理的な国民負担の下で、食料安全保障の確保を持続可能な方法により実現するための道である。(報告書:p117)
3)米・麦・大豆等について財政負担の状況を見てみると、主食用米以外の作付に対して所得補填を行う「水田活用の直接支払交付金」や、小麦等について生産コストと販売価格の差額を補填する「畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)」等の経営所得安定対策等として、年間5,000~6,000 億円規模の多額の財政支出を行っている現状がある。これらの土地利用型作物は、熱供給量の高さから食料安全保障上も重要性が高いと考えられるが、当初予算の2割~3割に当たる規模の財政負担の在り方がそれに見合ったものかどうかは常に検証が必要である。(報告書:p117,118)
4)(新基本法)改正前は唯一の目標とされていた食料自給率は、国内生産と消費に関する目標の一つとして相対化され、そのほかに食料安全保障の確保に関する事項の目標を設定することとされており、国内生産の増大のみを重要視する考えには立っていない。このうち、輸入に関しては、現在の輸入品の大宗が、政治経済的に良好な関係の国からのものであることを踏まえれば、こうした品目については、あえて国民負担で国内生産を拡大するということではなく、輸入可能なものは輸入し、ほかの課題に財政余力を振り向けるという視点も重要である。(報告書:P118)
頭のよい官僚たちや都会育ちの政治家達が信じているこの新自由主義の考え方は、最終的には、「格差社会」の拡大にも繋がっているのです。
規制緩和と競争原理が最適なパラダイムだと信じている霞が関の官僚達にとっては、「日本における企業的大規模農業の実現」は疑うことのない当然の事実だと思い込んでいるのです。
しかし、この官僚達が常識だと思っている「日本における企業的大規模農業の実現」は、日々、作物を育てている現実の農家にとっては「常識」ではなく、まさに、「見果てぬ夢」なのです。
稲田宗一郎(いなだ そういちろう)