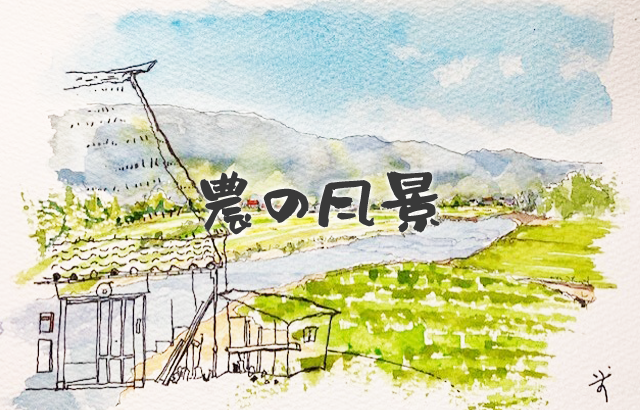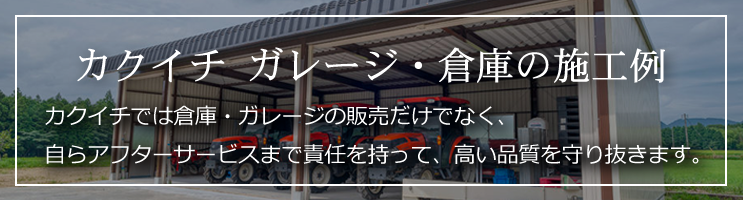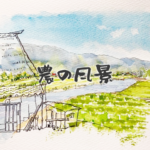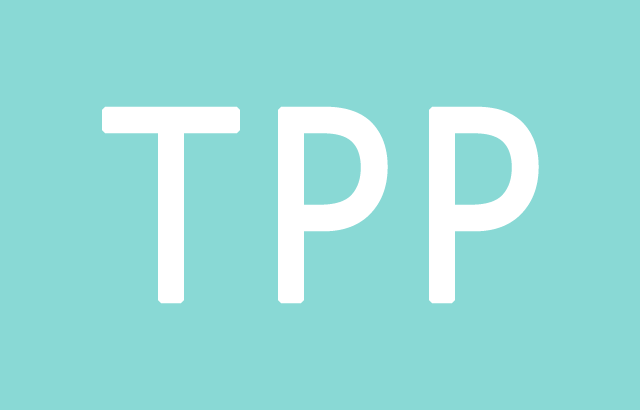昨年12月のはじめに、『ルバイヤートを楽しみながらワイナリーと消費者を繋ぐ交流の場を作る』で、丸藤ワイナリーのオーナー大村さんと懇談するために勝沼に行った。
丸藤ワイナリーは、明治23年5月に現オーナーの曽祖父にあたる大村治作氏が自宅の庭に小さな葡萄酒醸造所を造った時から始まり、以来、親子4代にわたり「一人でも多くの方々に本物のおいしさをわかっていただく」ことを喜びに、在来品種甲州や欧州系品種カベルネ・ソーヴィニヨン、プティヴェルド、シャルドネなどの栽培・醸造を繰り返しながら、「世界に誇る日本のワイン」をめざし、歩んできたワイナリーだ。

当日は、まず、仲間の車で、ぶどうを持った薬師如来像で知られる大善寺を参拝し、そのあと、手打ちうどん信玄で、小指ほどの太さのうどんと鳥もつ煮で一杯やり、ぶどうの丘の天空の湯に浸かり、早めにホテルにチェックインした。
高台にあるホテルの食堂から、缶ビールを飲みながら勝沼の景色を眺めたのだが、ぶどう畑が夕闇の薄い光の中にボヤッと浮かんだ風景は、一枚の西洋画のようで美しかった。
17時30分、迎えに来てもらったタクシーで、本日の懇談の舞台であるBISTRO Mille Printemps(ビストロ・ミル・プランタン)に向かった。この店のオーナーは、昔、銀座レカンでソムリエをやっていた人で、オーナーの大村さんとも懇意でルバイヤートワインを扱っている。
2020ルバイヤート甲州で始まった懇談会でオーナーからワインの話を聞いた。
「ワインの品質を決めるのは何ですか?」
と僕は、素朴に質問した。大村さんは、即座に、
「品質の90%は原料のブドウによって決まります」
と答えてくれた。
僕は、その年の夏に、小説『アンコンシャス・ヒポクラシー 尖った臭い』の執筆で滞在していた信濃追分の出来事を思い出した。その時、知り合いの中軽井沢に住んでいるエネルギー関連会社の会長と食事した時の会話を思いだしたのだ。その時、会長は、「東御市のワイナリーのオーナーから「やっとシャルドネらしいブドウができた」と報告があったので、明日、試飲に行くから一緒にどうですか」と言っていた言葉を思いだしたのだ。

この話を聞いた大村オーナーは、
「確かにシャルドネらしいシャルドネを日本で作るのは難しい」
と即座に答えた。
「シャルドネらしいシャルドネ?それってどう言うことですか?同じシャルドネではないのですか?」
「稲田さん、シャルドネは、ご存知のように、フランスのブルゴーニュ地方原産の白ワイン用ブドウ品種です。しかし、同じシャルドネでも、産地や土壌や気候の違いで様々な味わいを持つワインになるのです」
「それって、同じシャルドネを使った白ワインでも勝沼の白ワインとブルゴーニュ地方の白ワインは全く別物ってことですか?」
「厳密言えばその通りです。例えば、ブルゴーニュ地方の中でもピュリニー・モンラッシェ地区の白ワインは他のブルゴーニュ地方の白ワインとも別物です。なぜならば、2つの地区のブドウ畑の環境が異なるからです」
「それならば、日本のワインをブルゴーニュワインやナパワインと比較する、あるいは目指すってこと自体、おかしいってことですよね」
「そう言うことです。日照時間・気温・降水量などの気象条件や地質・水はけなど土壌の状態、斜面・平地といった地形が違えば同じ品種のブドウでも品質は違うのです。ワイン造りを厳密に捉えれば、ワイン造り=ブドウ造り=ブドウ畑造りってことになるのですよ」
「ふーん、ワイン造りって、ブドウを絞ったりする技術がメインだと思っていたのですが、原点はブドウ畑造り、つまり、農業ってことなのですね。最初にオーナーが「品質の90%は原料のブドウ」って言っていた意味がやっとわかりました」
「そうです。今、日本全国でワイン造りが盛んで、それ自体は嬉しいことですが、本当の意味の「ブドウ造りへのこだわり」が少なくなっている事が少し心配です」
僕は、その昔、何かの小説で、「この白ワインは干し草の匂いがする」という表現があったことを思い出した。そのときは、ワインの味・香りを上手く表現することがワイン通なのかと思ったりしたが、そんなことはカッコマンの都会人の勝手で、ワインの本質は、当たり前の事だがブドウで、その心の真髄はブドウ畑であり農業なのだと教えられた。
気がつくと、ルバイヤートの白ワインと赤ワインが、それぞれ、2本づつ空いていた。
稲田宗一郎(いなだ そういちろう)